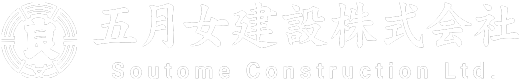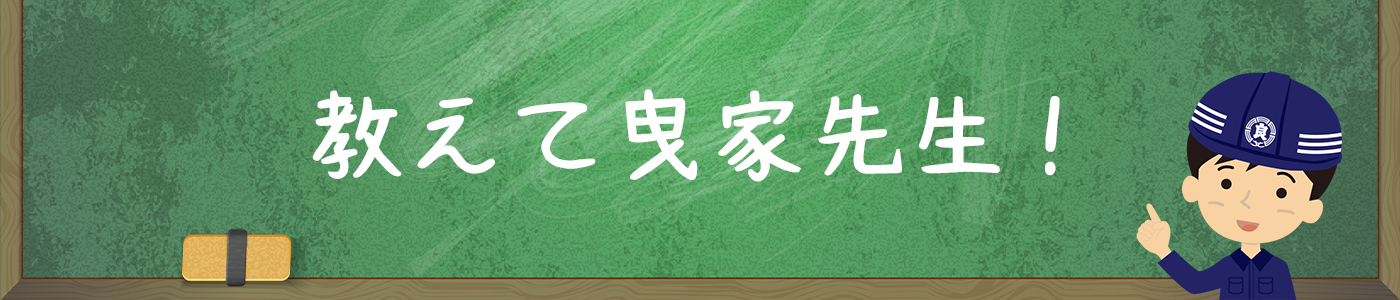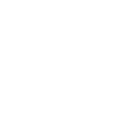【曳家】距離・回転と費用の関係|リスクを抑えて費用を節約するコツ
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! 第九話 ~絶対に損しない距離のコツ~ 費用やリスクをわかりやすく解説!
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
こんにちは曳家先生です。前回は、「絶対に損しない建築確認のコツ」についてお話ししました。今回は、お客様から「建物の移動距離で金額ってどのくらい変わるの?」、「曳家ってどのくらいの距離動かせるの?」という質問を頂く機会が多い「距離」、そんなよくある質問をもとに「絶対に損しない距離のコツ」についてお話しします。
そもそも距離とは?
改めて「距離」ですが、そもそも距離とは何でしょうか。Wikipediaによると「距離(きょり、distance)とは、ある2点間に対して測定した長さの量をいう。」とあります。「距離」は曳家工事の工事金額にとっても重要なポイントです。そのため、曳家工事に関する距離についての概要を知ることが大切です。
まず「絶対に損しない距離のコツ」を知るためには、曳家と距離との関係がどのようなものか知る必要があります。
それでは最初に「距離」についてよくある2つの質問に答えていきましょう。
建物の移動距離で金額ってどのくらい変わるの?
もしかすると、距離と工事金額についての質問は頂く質問の中で一番多いものかもしれません。

一般社団法人日本曳家協会による制作出版の「曳家業務 曳家のガイドブック基礎知識」によると、平米単価に対して、10m毎に10%アップとあります。つまり、500万円の曳家工事なら、10mの移動で550万円(500万円+50万円)、20mの移動で600万円(500万円+100万円)といった形になります。また、曳家工事によくある建物の仮置き、曳き戻しで合わせて20%(100万円)増加、方向転換で10~20%(50~100万円)増加となります。ただし、ここで注意しなくてはいけないのが、短い距離の場合です。例えば、最終的に5mだけ移動でコンクリート基礎は元々の場所に置いていく場合などは、元々の基礎から逃げた形で仮曳、仮置きで曳き戻し(移動30m+戻し20m等)となるので、金額が上がることがあります。新築に比べ、一般的に1/3~1/2と言われる曳家工事の工事価格ですが、その他建物の構造や上げ下げ高さ、回転、障害物など様々な条件が関連しますので、詳しくは近くの曳家業者、もしくは五月女建設「簡単見積りフォーム」でご相談ください。
もっと詳しく知りたい方は 「教えて曳家先生! 第二話 ~絶対に損しない曳家費用のコツ~」
曳家の費用は距離でどう変わる?費用の内訳と変動要因
曳家費用は、建物の構造、重量、移動経路の複雑さなど、様々な要因によって変動しますが、移動距離もまた、費用に大きな影響を与える要素の一つです。ここでは、移動距離が曳家費用の内訳にどのように影響するのかを詳しく見ていきましょう。
人件費:移動距離による作業時間の増加
曳家工事では、建物を移動させる作業員の人件費が大きな割合を占めます。ですから移動距離が長くなるほど、当然ながら移動作業にかかる時間も増加し、それに伴い、作業員の人件費も増加します。特に、長距離の移動では、段取り変えによる移動速度の低下や休憩時間の確保なども考慮する必要があるため、想定以上の時間がかかることもあるのです。
運搬費:長距離輸送に必要な特殊車両と燃料費
曳家では、建物を安全に移動させるために、使用される枕木、レールなどの資材の量が増加されます。長距離の移動となると、これらの曳き方資材の運搬費用や運搬にかかる燃料費が嵩みます。また、移動経路によっては、大型車両の通行許可申請が必要になる場合もあり、そのための費用も発生します。
諸経費:許可申請費用、保険料など
敷地を跨ぐような長距離の曳家では、道路使用許可申請や建築確認申請など、各種の許可申請が必要になる場合があります。これらの申請には費用がかかります。また、長距離移動中の予期せぬ事態に備えて、保険に加入する場合もあり、その保険料も諸経費として計上されます。
曳家の技術:長距離になるほど難易度は増す?
短距離の曳家と比べて、長距離の曳家は技術的な難易度が格段に高くなります。ここでは、長距離曳家特有の技術的な課題について解説します。
安全対策:長距離移動における家屋の保護
長距離の移動中には、振動や衝撃によって家屋が損傷するリスクが高まります。そのため、事前の入念な調査に基づいた適切な補強工事が不可欠です。移動中も、常に家屋の状態を監視し、必要に応じて補強を行うなど、細心の注意を払う必要があります。
経路選定:電線、道路、橋梁などの障害物
長距離の移動では、移動経路の選定が非常に重要になります。電線、電柱、その他工作物、段差など、様々な障害物を避けながら、安全かつスムーズに移動できる最適なルートを選定する必要があります。場合によっては、関係機関との協議や特別な措置が必要になることもあります。
基礎の補強:長距離移動に耐えうる強度
建物の基礎は、移動中の荷重や振動に耐えられるように補強する必要があります。特に長距離移動の場合、基礎にかかる負担が大きくなるため、地盤や基礎にかかる鋼材により強固な補強が求められます。基礎の補強が不十分だと、移動中に建物が破損する危険性があります。
30秒で簡単入力、無料で曳家相談!
曳家の期間:距離が工期に与える影響
曳家工事の期間は、建物の規模や構造、移動距離、経路の複雑さなどによって異なります。ここでは、移動距離が工期に与える具体的な影響について見ていきましょう。
事前調査:長距離になるほど詳細な調査が必要
長距離の曳家では、移動経路の詳細な調査が不可欠です。道路の幅、勾配、交通量、電線や埋設物の位置など、様々な情報を事前に把握する必要があります。調査範囲が広くなるため、当然ながら調査にかかる時間も長くなります。
移動作業:移動速度と休憩、夜間作業の可能性
曳家の移動速度は、安全性を考慮して非常にゆっくりと行われます。長距離の移動となるほど、移動作業にかかる時間も長くなります。また、作業員の休憩時間や、交通への影響を考慮して夜間作業を行う必要が出てくる場合もあります。
復旧作業:移動後の微調整と確認
建物を移動させた後は、基礎との接合部分の微調整や、建物の傾きなどを確認する復旧作業が必要です。長距離移動の場合、移動中に建物に歪みが生じる可能性もあるため、より慎重な確認作業が求められます。
建物の移動距離が伸びると建物が壊れないの?
距離が伸びても建物はひび割れを作ることなく移動することは可能です。ただしそのためには厳密な施工管理が必要になります。なぜなら建物の移動距離が伸びることで移動途中での地盤の土質や支持力の変化が起き、建物のひび割れ・損傷のリスクが増える事もあります。ですので、必要に応じて枕木の本数を増やしたり、敷鉄板やコンクリートで必要な支持力を確保することが大切です。その上でレベル等の測量機によって建物の道となるレール高さの管理を行うことで、建物のひび割れ・損傷を未然に防ぐことができます。施工事例や作業計画について曳家業者に尋ねることで、その業者の施工管理体制や作業に対する基本姿勢などを調べることができるので、建物の移動に関してご不安やご不明な点がある方はどんどん質問してみてくださいね。

またこれらの質問を解決するためには、曳家業者に依頼して、以下の条件で具体的に確認しておくことが大切です。
費用やリスクの確認方法
1.移動計画図・建物図面を確認してもらう
建物の移動計画の図面や建物の構造のわかる図面を用意して曳家業者に確認してもらうことで、実際の建物の移動距離や回転角度、工程などを把握することができます。また曳家業者はこれらの図面を確認することでより正確なお見積り作りをすることができます。
2.建物や周囲の状況を現地調査してもらう
現地調査をすることによって、今ある建物に既にある腐食や損傷、建物の周囲にある障害物や曳家計画箇所の土質状況、その他電線、上下水道・ガスなどの状況、周囲の道路状況などを確認してもらうことができます。また実際の建物を移動するにあたってのリスクについても検討をすることができます。また近年だとLineやZoom、Googlemeetなどを用いたリモートでの現地調査を取り入れている曳家業者もあるので、ぜひホームページやSNSで調べてみてください。
3.曳家工事をしている現場を見に行ってみる
ご近所でもし曳家工事をしている現場があったら、ぜひ直接現場に行って作業の状況を確認してみましょう。というのも、各々曳家業者にとって品質管理、工程管理、安全管理に大きな違いがあるため、一概に同じ移動距離であってもその作業内容や見積に大きな違いが出ることがあるのです。大切な想い出のたくさんつまった建物を任せるにはどんな曳家業者が適切かを直接見て、必要であれば現場の作業員と話をして判断することは、後々のリスクを大幅に軽減する大切な一歩ことになります。もし近くで曳家工事をしている現場を見つけることができない場合には曳家業者さんに直接連絡を取ることで、近くの工事現場を紹介してもらうことができます。
30秒で簡単に入力、無料でお見積り
図面を用意すると簡単にできます
番外編)曳家ってどのくらいの距離動かせるの?
 結論から言ってしまうと、家の重さ、道路の状況、曳家業者の技術の条件がそろえば、「どれくらいでも曳けてしまうという」のが答えになるかと思います。ただし、トラックに積むことができる重さは10~15tであるのに対し、建物の重さは木造住宅で基礎コンクリートを除いても30t~、鉄筋コンクリート造であれば200tを越える重量は当たり前なので、実際には難しそうですね。また道路幅、高さ、坂の傾きや交通規制による制限があるため、一般的には建物の移動は「敷地内」もしくは「隣接敷地」に行うことが大半です。私たい五月女建設の場合では、大谷石造の石蔵を道路を渡って170m、瓦葺木造神社を106m移動した経験があります。
結論から言ってしまうと、家の重さ、道路の状況、曳家業者の技術の条件がそろえば、「どれくらいでも曳けてしまうという」のが答えになるかと思います。ただし、トラックに積むことができる重さは10~15tであるのに対し、建物の重さは木造住宅で基礎コンクリートを除いても30t~、鉄筋コンクリート造であれば200tを越える重量は当たり前なので、実際には難しそうですね。また道路幅、高さ、坂の傾きや交通規制による制限があるため、一般的には建物の移動は「敷地内」もしくは「隣接敷地」に行うことが大半です。私たい五月女建設の場合では、大谷石造の石蔵を道路を渡って170m、瓦葺木造神社を106m移動した経験があります。
また日本における長距離の曳家工事の代表的な例は足利フラワーパークの「樹齢130年の藤棚」の移植が有名です。その移動距離なんと20km! とても感動的なストーリーなので「奇蹟の大藤」、ぜひチェックしてみてくださいね。

【曳家の距離よくあるご質問(FAQ)】

Q1. 最大でどれくらいの距離まで曳家できますか?
A1. 技術的には数キロメートルに及ぶ長距離の曳家も可能ですが、費用や法規制、工事支障物などの制約により、一般的には数百メートル程度が上限となることが多いです。
Q2: 曳家工事の費用は、建物の移動距離によってどのくらい変わりますか?
A2: 一つの目安として、一般社団法人日本曳家協会のガイドブックでは「移動距離10m毎に工事費が10%アップする」とされています。例えば500万円の工事の場合、10mの移動で50万円、20mの移動で100万円が追加される計算です。また、建物を一度仮置きする「曳き戻し」や建物の向きを変える「方向転換」でも、それぞれ10~20%程度の追加費用が発生することがあります。
Q3: なぜ移動距離が長くなると、費用が高くなるのですか?
A3: 移動距離が長くなると、主に以下の3つの費用が増加するためです。
- 人件費: 移動にかかる作業時間が長くなるため、作業員の人件費が増加します。
- 運搬費: 移動に使うレールや枕木といった資材の量が増え、それらを運ぶための運搬費や燃料費がかさみます。
- 諸経費: 敷地を越えるような長距離移動では、道路使用許可の申請費用や、万が一に備えるための保険料などが別途必要になる場合があります。
Q4. 費用を抑えるためにできることはありますか?
A4. 移動距離を短縮できる可能性がないか検討したり、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。また、工事時期を調整することで費用を抑えられる場合もあります。
参考:曳家工事での失敗回避のコツ!費用・工事の失敗を避ける方法を解説!
Q5: 長距離の曳家工事は、技術的にどのような点が難しくなりますか?
A5: 長距離の曳家は、短距離に比べて以下の点で技術的な難易度が格段に高くなります。
- 安全対策: 移動中の振動や衝撃による建物損傷のリスクが高まるため、より入念な補強工事と移動中の監視が不可欠です。
- 経路選定: 電線、電柱、道路の段差といった様々な障害物を避け、安全に移動できる最適なルートを見つける必要があります。
- 基礎(土台)の補強: 長い距離の移動による大きな負担に耐えられるよう、移動の土台となる部分により強固な補強が求められます。
Q6: 建物を長い距離移動させても、ひび割れなどの損傷は起きないのでしょうか?
A6: はい、適切な施工管理を行えば、ひび割れなどを起こさずに長い距離を移動させることは可能です。長距離移動において、特に雨季などは地面の状態(地盤)が変化しやすい場合もあるため、枕木の本数を増やしたり敷鉄板を敷いたりして建物を支える力を確保します。その上で、沈下量を逆算し、測量機を使ってレールの高さを精密に管理することで、建物への負担を最低限に減らし損傷を防ぎます。
Q7: 曳家工事を依頼する前に、費用やリスクを正確に確認するにはどうすればよいですか?
A7: 後悔しないために、以下の3つの方法で業者に確認することが重要です。
- 図面で確認してもらう: 建物の図面や移動計画図を業者に見せ、正確な見積もりと工程を把握します。
- 現地調査をしてもらう: 業者に現地を調査してもらい、建物の状態、周辺の障害物、道路状況などを確認し、具体的なリスクを洗い出してもらいます。(※近年はリモートでの調査に対応する業者もあります)
- 工事現場を見に行く: 実際にその業者が行っている工事現場を見学し、作業の質や安全管理体制を自分の目で確かめることが、最も信頼できる判断材料になります。
Q6: 【番外編】実際、建物はどれくらいの距離まで動かせるのですか?
A6: 理論上は、条件さえ揃えば「どこまででも動かせる」と言えます。しかし、実際には建物の重さ(木造住宅で30t以上)や、道路の幅・高さ、交通規制などの制約があるため、ほとんどの工事は「同じ敷地内」または「隣接する敷地」への移動となります。過去には、石蔵を170m移動させたり、足利フラワーパークの有名な藤棚が20kmも移植されたりした長距離の事例もあります。
私たち五月女建設では神社とその鳥居を水平距離108m、高さ9m移動した事例もあります。↓
ーーー
まとめ|距離よりも長く続く未来へのお付き合い
曳家工事を行っていると現場のご近所に住まわれている方から
「一日でこんなに動いたんだね!凄いね!」
「五月女さん凄い技術だね!」
とお褒めの言葉や驚きの感想を頂くことがあります。私たちは職人ですから、やはり自分たちの技術が評価されることはとても嬉しいことなのですが、やはり一番うれしいのは、お客様に無事に現場を引渡しできる瞬間であり、それより何にも代え難い喜びは工事完了後、何年も経ってからお客様からご連絡を頂けるときです。
「五月女さん、久しぶりで悪いんだけど○○頼める?」
こういったお言葉を頂いた時こそ、お客様との時間を越えた信頼関係が築けたことが実感できるからです。
ーーー
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
もし身近に信頼できる曳家さんがいない場合は日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女がどんな小さなことでもお答えします。ぜひお悩みを曳家先生へのウェブ相談、もしくは五月女建設のお問合せフォームでご連絡くださいね。
あなたの身に寄り添った立場で法律面、施工面、費用面など持てる知識と経験の限り、誠心誠意お答えさせて頂き、あなたの「絶対損しない曳家工事」に協力させて頂きます。
参考文献
・曳家業務 曳家のガイドブック基礎知識(一般社団法人日本曳家協会)