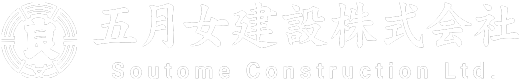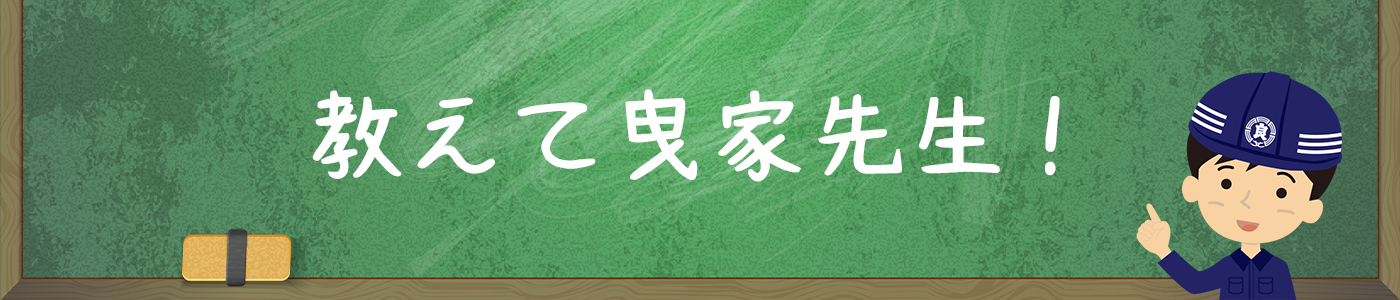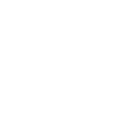【曳家工事】失敗しないためのチェックポイント|後悔しないための完全ガイド
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! 第四話 ~絶対に損しない失敗回避のコツ~
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
こんにちは曳家先生です。第三回目の前回は、「絶対に損しない業者のコツ」についてお話ししました。今回は、家を曳家する際に必ずと言っていいほど関わってくる小さな失敗から大きな失敗まで、「絶対に損しない失敗回避のコツ」についてお話しします。
曳家工事を行う際には、様々な失敗が起こる可能性があります。例えば、工事中に事故が起こる、工期が遅れる、工事費が当初の見積もりよりも高くなる、などの失敗があります。
これらの失敗を回避するためには、曳家工事の前に、失敗の原因を理解しておくことが大切です。
「・・・もしかして、この記事を最後まで読まずに曳家工事を始めようとしていませんか?」
一番の失敗は、この文章を最後まで読まずに曳家工事を始めてしまうことかもしれません。
さて、冗談はさておき曳家をする際に起こる失敗の原因は、大きく分けて3つあります。
事前の準備が重要!
「じゃあ、どうすればいいの…?」
そう思ったあなた! 安心してください。 これらの落とし穴は、 事前の準備 をしっかり行うことで 回避できる ん です。
つまり、 業者選び 、 打ち合わせ 、 事前調査 、この3つが 曳家工事成功のカギ となるのです!
「具体的に、どんな失敗例があるの…?」
と思った方は、ぜひ読み進めてください! 次は、曳家工事を専門とする “曳家先生” が目撃した、 衝撃の失敗事例 をご紹介していきます!
曳家の悲劇?実際に聞いた失敗事例とその原因
「曳家工事って、家を動かすだけでしょ? 何がそんなに難しいの?」
なんて思っていませんか? 実は曳家工事、 想像以上にデリケートでかつ複雑で高度な作業 なんです。
今回は、そんな曳家先生が実際に聞いた失敗事例 を通して、曳家工事の 落とし穴 を詳しく解説していきます! あなたの家を守るためにも、ぜひ最後まで読んでくださいね。
失敗事例①:建物を上げるときの損傷
曳家工事の基本は、 建物をジャッキアップ すること。
しかし、建物の 重量 や 形状 、 材料の性質 などをきちんと把握していないと…
- ジャッキの台数が足りない
- 鋼材の本数が足りない
- ジャッキや鋼材の位置が適切でない
- 建物の弱い場所を理解していない
といったことが起こり、 家がうまく持ち上がらない ことがあります。
さらに、 基礎共工法 の場合は、基礎下に穴を掘るため、 雨 が降ると 地盤が弱く なり、家が 傾いてしまう こと もあるんです!
「そんなの、業者がちゃんと考えてくれるでしょ?」
そう思いたい気持ちは分かります。 しかし、中には 「コスト削減!」 「面倒くさい!」 という理由で、 必要な作業を省いてしまう 業者もいるのが現実…。
- ジャッキを増やすと、基礎を壊す場所、枕木の設置場所、手間が増える
- 雨水排水路や排水ポンプ、シート設置などの雨の養生は手間がかかる
- 基礎下に穴を掘るのは時間がかかる
…などなど、業者にとっては “面倒な作業” を減らしたいという気持ちも分かりますが、 それによって 家が壊れてしまっては元も子もありません。
失敗事例②:移動中の建物への損傷
せっかく家が持ち上がったと思っても、 移動中 に 思わぬトラブル が発生することも…!
- 軟弱な地盤 の上に建物を移動させたら、 家が傾いて しまった…
- 玉石の石垣 の上に建物を置いたら、 石垣が崩れて 外壁にヒビ が入ってしまった…
- 建物移動のための道(レール)が水平でないため、建物が歪んでしまった…
なんてことも、実際に見たことがあります。
曳家工事には、 建物 だけでなく、 地盤 や 材料 に関する 幅広い知識 が必要不可欠なんですね。
失敗事例③:家が地面に着地した瞬間の損傷
「やっと移動できた…!」 と安心したのも束の間、 建物を下げる時 にも 危険 が潜んでいます。
実は曳家作業においては家が地面から離れた直後 や 着地した直後 が、 最もヒビ割れが起こりやすい タイミングなんです。
例えば、建物を下げる時の問題点は
- 建物を支える面積が少ない
- 基礎共工法でストップジャッキが少ない
- 耐圧版の数や強度が足りない
- ジャッキ(建物)が均等に下がっていない
…など、様々な要因が考えられます。
さらに、 地震 などの揺れに耐えられるような しっかりとした構造 で曳家工事が行われているかどうかも、 重要なポイント です。
失敗事例④:工事後も安心できない…?
「工事が終われば、もう安心!」
…と思いたいところですが、 工事後 に 家の傾き や ヒビ割れ が発生するケースも…。
これは、 地盤改良 が不十分だったり、 基礎工事 に問題があったりすることが原因として考えられます。
なぜ起こる?曳家で失敗してしまう理由
これらの失敗事例からわかるように、曳家の失敗には様々な原因が考えられます。ここでは、主な理由を掘り下げて解説します。
事前調査の不足とリスクの見落とし
曳家を成功させるためには、事前の徹底的な調査が不可欠です。地盤の状態、建物の構造、移動ルート上の障害物など、あらゆるリスクを洗い出す必要があります。例えば、築30年を超えるお風呂・台所など水回りの土台、柱は湿気による腐食があることもあったり、建造当初にはなく、届け出もしていない増築部分。また建物の所在地や構造に関わる法律など、この調査が不十分だと、予期せぬトラブルに見舞われる可能性が高まります。
建築当時の施工不良
曳家を行う建物が建造されたときの施工不良も曳家工事の潜在的なリスクとして存在します。設計図面どおりに基礎が作られていなかったり、あるべき柱がない、必要な金具がない、あるべき鉄筋が配置なかったり、必要な鉄筋のかぶりが確保されていないなど、建造当時の施工不良は住んでいる建物に見えない損傷を引き起こすだけではなく、曳家工事でも余計な手間を発生させたり、建物損傷のリスクに繋がります。
経験不足や技術力不足の業者による施工
曳家は専門的な知識と高い技術力が求められる工事です。経験の浅い業者や、技術力が低い業者に依頼してしまうと、安全管理が疎かになったり、適切な工法を選択できなかったりする可能性があり、失敗につながるリスクが高まります。例えば専門的な知識でも曳家工事では、地盤・土質・コンクリート・構造・材料・力学・法律・安全など多種にわたる専門知識が求められます。また曳家を行う建物と同種の工事の経験、またバラエティある工事の経験を乗り越えて生まれる技術力も必要です。つまり、知識だけでも、技術力だけでも安心安全な曳家工事は難しいと言えます。
天候不良や予期せぬ自然災害
雨天や強風などの悪天候は、曳家作業に大きな影響を与えます。また、地震などの予期せぬ自然災害も、曳家中の建物に致命的なダメージを与える可能性があります。これらのリスクを考慮した計画と対策が必要です。例えば、上がっている途中の建物の転倒リスクを下げるためにどんな取り組みをしていたか、しようとしているか。土の性質を理解して、雨の対策をとっているかなど、
コミュニケーション不足による連携ミス
曳家工事は、多くの作業員や関係者が連携して行う作業です。業者と依頼主の間、あるいは作業員間のコミュニケーションが不足すると、情報伝達の遅れや誤解が生じ、連携ミスによる事故やトラブルにつながる可能性があります。またお客様との打ち合わせ内容をきちんと現場に反映されないこともコミュニケーション不足によって引き起こされます。
知っておくべき!曳家失敗のリスクと代償
曳家が失敗した場合、様々なリスクと代償が発生します。事前にこれらのリスクを理解しておくことは、曳家を検討する上で非常に重要です。
建物の倒壊や重大な損傷
最悪の場合、曳家中の建物が倒壊したり、重大な損傷を受けたりする可能性があります。これは、建物の価値を著しく損なうだけでなく、人命に関わる重大な事故につながる可能性もあります。
工期の遅延と追加費用の発生
失敗によって工事が中断したり、やり直しが必要になったりすると、工期が大幅に遅延する可能性があります。また、追加の工事費用や損害賠償が発生するなど、経済的な負担も大きくなります。
近隣住民とのトラブル
曳家工事は、騒音や振動、交通規制など、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。着工前に近隣の方々へ充分な挨拶を行わないことで、クレームがあったり、事故のもとに繋がります。また失敗によって工事が長引いたり、建物の倒壊などで被害を与えてしまったりすると、近隣住民との深刻なトラブルに発展する可能性があります。
精神的な負担と再度の曳家の困難性
曳家の失敗は、依頼主にとって大きな精神的な負担となります。また、一度失敗した建物を再度曳家することは非常に困難であり、多くの場合、建て替えを選択せざるを得なくなります。例えば、外壁のひび割れは補修によって一見直ったように見えても、内側の構造の損傷を後から直すには、一部解体工事が必要になるため、手間も費用も高額になること間違いないのです。
曳家工事の失敗、もう怖くない! プロが教える、成功を掴む3つの秘訣
「曳家工事で失敗したくない…!」
「でも、どうすればいいか分からない…」
そんな曳家工事の 成功を左右する 3つの重要ポイント を、 分かりやすく解説 します!
これさえ押さえれば、 失敗のリスクを大幅に減らし 、 安心して曳家工事に臨める ようになりますのでご参考ください。
業者選びは慎重に!|業者選びのチェックポイント
曳家工事の成功は、 業者選び でほぼ決まると言っても過言ではありません。
「じゃあ、どんな業者を選べばいいの…?」
と思ったあなたへ。 業者選びで 失敗しないためのポイント をまとめました!
- 複数の業者から相見積もりを取る
- 複数の業者を比較することで、 適正な価格 と サービス内容 を把握 できます。
- 業者の資格や実績を確認する
- 曳家工事には 専門的な知識 と 経験 が必要です。 信頼できる資格 を持っているか、 実績 が豊富かどうかを確認しましょう。
- 保険の加入状況を確認する
- 万が一の事故に備え、 適切な保険に加入しているか を確認しましょう。
- 見積もりの内容を細かくチェックする
- 見積もりは 詳細な内訳 まで確認し、 不明点 は必ず質問しましょう。 「別途費用」 の記載にも注意が必要です。
- 過去の事例やお客様の声を参考にする
- ホームページや口コミサイトなどで、 過去の施工事例 や お客様の声 をチェックしましょう。
- 担当者の対応をチェックする
- 質問に丁寧に答えてくれるか 、 親身になって相談に乗ってくれるか など、担当者の対応も重要なポイントです。

ーーー業者に聞いておきたいことーーー
- 「曳家工事の経験はどれくらいありますか?」
- 「保有している資格はありますか?」
- 「今回の工事には、何台のジャッキを使いますか?」
- 「工事中の安全対策はどうなっていますか?」
- 「何かトラブルがあった場合は、どのように対応しますか?」
…など、 疑問に思ったことは遠慮なく質問 しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
打ち合わせは密に!|打合せのチェックポイント
業者との 打ち合わせ も、曳家工事の成功には欠かせません。
「どんなことを話せばいいの…?」
そんな方のために、 打ち合わせで確認すべきポイント をまとめました!
- 自分の希望を明確に伝える
- 「いつまでに工事を終わらせたいか」 「予算はどれくらいか」 「どんな家にしたいか」 など、 希望を具体的に 伝えましょう。
- 業者の説明をよく理解する
- 専門用語 を使わずに、 分かりやすく説明してくれるか 、 疑問点に丁寧に答えてくれるか を確認しましょう。
- 必要があれば記録を残す
- 口約束 だけではなく、 重要なことは書面で残す ようにしましょう。
- 担当者の態度をチェックする
- 誠実 で 熱意 があり、 最後まで責任を持って対応してくれるか を見極めましょう。
- 不安をあおるような発言をする業者には注意!
- 過度に不安をあおったり 、 他社の悪口を言ったり 、 契約を急がせる ような業者は避けましょう。

ーーー打ち合わせで確認しておきたいことーーー
- 「建築基準法などの関連法令に精通していますか?」
- 「見積もり金額が変わる可能性はありますか?」
- 「工事完了後のアフターサポートはありますか?」
…など、 不安なことは事前に解消 しておきましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事前調査を入念に!|事前調査のチェックポイント
曳家工事を行う前に、 事前調査 を入念に行うことも大切です。
事前調査では、以下の点を確認しましょう。
- 現在の建物の状態
- 地盤 、基礎 、建物の構造 など、現状を把握しておくことが重要です。
- 業者の評判
- インターネットなどで、業者の評判を調べてみましょう。
- 行政とのコミュニケーション
- 曳家工事には、行政への手続きが必要な場合があります。 必要な手続き や 注意点 を確認しておきましょう。
- 現地調査への立ち会い
- 業者による 現地調査 に立ち会い、 説明を受ける ようにしましょう。 疑問点 はその場で質問しましょう。

ーーー事前調査で確認しておきたいことーーー
- 「地盤や周辺環境の調査はどのように行いますか?」
- 「建物の図面や過去の改修履歴は確認しましたか?」
- 「床下や土台の状況は確認しましたか?」
- 「水道・電線・ガスなどの設備はどうなりますか?」
- 「庭木や塀など、工事の支障になるものはどうなりますか?」
…など、 疑問に思ったことは遠慮なく質問 しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、ここまで家を移動する際に気を付けるべき失敗の原因と回避方法についてお話ししました。失敗は、誰にでも起こりうるものです。しかし、これらの対策を講じることで失敗を回避し、満足のいく曳家工事をするができるでしょう。
ーーー
もし失敗してしまったら?取るべき対応と注意点
万が一、曳家が失敗してしまった場合には、冷静に対処することが重要です。感情的にならず、以下の点に注意して対応しましょう。
まずは状況を把握し、業者と冷静に話し合う
まず、何が起こったのか、状況を正確に把握しましょう。その後、業者と冷静に話し合い、原因究明と今後の対応について協議します。感情的な言動は避け、建設的な話し合いを心がけましょう。
チェックポイント
- 建物には具体的にどのような損傷があるのか?
- 基礎や地盤に異常は見られるか?
- 給排水や電気、ガスなど設備への影響は?
- 失敗の原因は?
- 修復方法と費用の負担は?
- 今後のスケジュールは?
専門家への相談や法的手段も視野に入れる
業者との話し合いで解決が難しい場合や、専門的な知識が必要な場合は、第三者の弁護士や建築士などの専門家に相談することを検討しましょう。専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
また、失敗をした業者が前向きな話し合いを持たなかったり、建設的な提案がない業者であれう場合は必要に応じて、法的手段も視野に入れる必要があるかもしれません。
記録を残し、証拠を保全する
失敗の状況や業者とのやり取り、損害状況などを詳細に記録しておきましょう。写真や動画などの証拠も保全しておくことが重要です。これらの記録は、今後の話し合いや法的措置において重要な証拠となります。
まとめ
曳家の成功は事前の準備と業者選びが鍵
曳家は、建物を移動させるという特殊な工事であり、成功させるためには事前の徹底的な準備と、信頼できる専門業者選びが不可欠です。「これから曳家をする」という方の多くは、曳家に対する不安や疑問を抱えています。この記事を通じて、曳家のリスクを理解し、適切な対策を講じることで、安全で確実な曳家を実現していただければ幸いです。
大切なのは、その後の安心・安全・快適な暮らし|あなたのずっと隣にいる曳家さん
曳家工事は、単に家を移動させるだけの作業ではありません。それは、お客様の大切な家を守り、未来へ繋ぐための大切な選択です。そして、私たちは、曳家工事の専門家として、お客様の想いを理解し、寄り添いながら、最適なプランをご提案いたします。
大切なのは、その移動した後の建物で、お客様がどれだけ安心・安全・快適に住み続けることができるかということです。
私たちは、長期的な視点に立ったサポートとして、工事完了後も定期的に連絡を取り、建物の状態を確認します。万が一、不具合が発生した場合でも、迅速に対応いたします。
なぜなら私たち一人一人がお客様との繋がりを大切に、末永くお付き合いできる企業を目指しているからです。
ーーー
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
もし曳家工事のことでの事前調査や業者選び、打合せに関して不明、不安な点がありましたら、日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女が相談に乗りますので、どうぞご気軽に曳家先生へのウェブ相談、もしくは五月女建設のお問合せフォームで連絡くださいね。