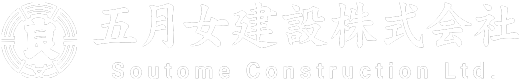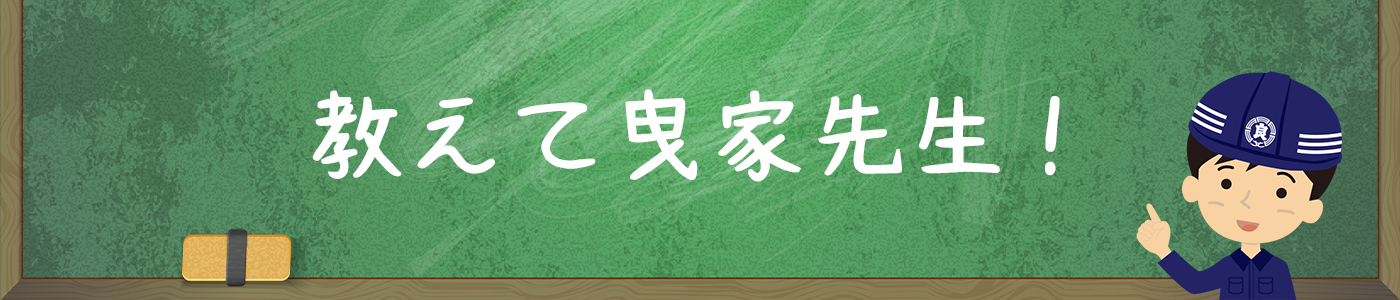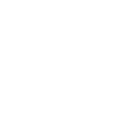【曳家 工法 徹底比較】失敗しない選び方!メリットデメリット・費用・期間を曳家先生が解説!
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! 第七話~絶対に損しない工法のコツ~ メリット・デメリットを曳家先生が解説
こんにちは曳家先生です。第六回目の前回は、「絶対に損しない地盤のコツ」についてお話ししました。今回は「曳家の工法」について学んでいきましょう。
家を移動する際には、工法選びがとても重要です。工法によって、工事品質、工事後の耐久性、工事価格などが大きく異なります。また、工法によっては、リフォームが必要になる場合もあります。一般的には工法は業者が決定しますが、損しないためにも曳家工事を検討する方は工法の特徴やそのメリットデメリットを知ることが重要です。
この「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」シリーズでは、曳家専門家の五月女建設が、絶対に損しないための知識をお伝えしています。今回は特に重要な「曳家工法」に焦点を当て、それぞれの特徴、メリット・デメリット、費用相場、期間、注意点などを徹底比較。
この記事を読めば、あなたの家と希望に最適な曳家工法を見極め、安心して工事を進めるための知識が身につきます。後悔しない曳家のために、一緒に学んでいきましょう!

曳家工事を選ぶ理由とは?曳家の三大メリット
建物の保存と移動|想い出・価値をそのままに!
曳家工事では、建物をそのまま移動させることができます。これにより、今まで積み重なってきたご家族との想い出、歴史的価値のある建築物や文化財を保存しながら、新しい場所へ移動させることができます。
コスト効果|近年ではさらにお得!
新築と比較して大幅に費用を抑えることができます。一般的に、曳家工事は建て直しの約1/3~2/3程度のコストで済むことが多いです。また新築工事に比べ、2020年以降の建築資材の高騰、建築廃材の処分費用の高騰の影響を受けにくくもあるため、近年ではさらに費用を抑えることが可能なのです。
参考記事:【北関東版】失敗しない!曳家費用の相場と補償金を徹底解説!|曳家見積もり前に
工期の短縮|スマート工期!
通常1~2ヶ月程度で完了するため、迅速な移転が可能です。
曳家工法、3つの工法の名称とその歴史と由来
曳家工法、3つの名称
曳家工法には大きく分けて、姿曳(すがたびき)移動工法(下腰工法)、基礎共(きそども)工法、腰付(こしつき)移動工法(上腰工法)の3つがあります。
腰(こし)とは剛性の強く建物を移動するためにその建物に連結する曳き方資材のことで、古くは303mm真四角の木材、尺角(しゃっかく)、現在ではH鋼、レール、角鋼管に代表されるものです。
その腰を、「柱に緊結するから『腰付移動工法(上腰工法)』」、「土台の下に設置するから『下腰工法(姿曳移動工法』」、基礎を一緒に移動するから『基礎共工法』」と覚えるとわかりやすいです。
曳家の歴史と原理
曳家工事の起源、古くは5000年前のエジプト、ピラミッド建築やストーンヘンジまで遡ります。日本においては紀元前5~7世紀に木製ソリである修羅(しゅら)から名古屋城天守閣工事の加藤清正の石曳きから現在へと続いていますが、その原理はテコとコロに代表される非常にシンプルな力学を応用した重量物を移動するための物理運動なのです。
参考記事:曳家とは?建物を移動する伝統工法
曳家工法の成り立ち
曳家工法の成り立ちは日本建築の構造の歴史に非常に強い関係性があります。
木組み工法、伝統工法と腰付移動工法
江戸以前の日本において、神社仏閣や伝統工法に代表される建築構造は主に木組構造が大部分占めており、その基礎部分は礎石に建物荷重を受ける柱が載るだけの「石場建(いしばだ)てで、また真壁構造で壁の撤去・復旧が比較的簡易にできたことから、腰付き移動工法が中心でした。
在来工法と姿曳移動(下腰)工法
明治以降における西洋文化の影響を受けた建築物は当初、自然石や加工された角石、長石などによって作られた布基礎石の上に敷土台・土台、礎石の上に木束を載せた構造で、のちにこれらの基礎はコンクリート、鉄筋コンクリートと変わっていきます。これらの工法は日本文化の発展と共に改良を加えられ、1960以降、ツーバイフォー工法と識別のために在来工法(木造軸組工法)と呼ばれるようになりました。この在来工法による建物は従来の日本建築に見られる木組工法と西洋建築の良いとこどりをしたような造りになっており、建物の重さを支える「柱」と、上からの重さを柱や基礎に伝える「梁」で骨組みを作り、補助金物を使用して屋根や壁を形成し、それらの荷重をコンクリート基礎に緊結された土台で受け造られています。そして、これらの建物は頑強な土台で建物上部を受けることができるため、その移転にはそれに適した姿曳移動(下腰)工法が採用されるようになりました。
ツーバイフォー工法、鉄筋コンクリート造建物と基礎共工法
1960年代以降に日本で急速に普及されたツーバイフォー工法とは使用する木材に2インチ×4インチ(38mm×89mm)のSPF材(スプルース、パイン、ファーの混合)と呼ばれる北米からの輸入材と構造用合板が主な構造の枠組壁工法のことを言います。このツーバイフォー住宅住宅は、耐震性、耐火性、省エネ、遮音性などに優れる一方、構造木材の柔らかさや土台・柱部材断面の小ささから、移転には姿曳移動(下腰)工法には向かないため、そのコンクリート基礎ごと移動する基礎共工法が採用されました。また、鉄筋の引っ張り強度とコンクリートの圧縮強度を活かし、耐久性、耐震性、耐火性に優れた鉄筋コンクリート造は、その基礎、床、柱、壁が一体となった構造のため、移転には基礎共工法が採用されました。
※また大手メーカーの国土交通省大臣認定を取った建物についても、その認定が基礎構造も含めることから、基礎共工法が採用されます。これらの建物において、コンクリート基礎を離脱して曳家工事を行うと契約時に定められた保証期間が終了しなくとも、メーカー保証が切れ、無料修理が受けられなくなり、雨漏りなどの修理には高額な費用が掛かることがあります。
自分の建物に合った工法は何?
つまり、家を移動する際には、建物の構造に合った工法を選ぶことが大切です。例えば、建物を建てた年の建築基準法、もしくは現在の建築基準法に対応できるような工法を選ぶ必要があります。また、工法によってはコンクリート基礎部分や壁部分に欠損部を作ることもあるため各工法の特徴・メリット・デメリットを知ることが大切です。
メリットとデメリットを比較検討する
工法には、それぞれメリットとデメリットがあります。例えば、下腰工法は価格や施工性に優れていますが、基礎コンクリートの欠損補修を行う必要があり、古いブロックを用いたタイプのお風呂場の移動は難しいというデメリットがあります。一方、基礎共工法は価格が高いですが、新築時の耐震性などの性能をそのまま維持して移動することができるというメリットがあります。そのため、メリットとデメリットを比較検討して、自分の大切な建物に合った工法を選ぶことが大切です。
それではどんなポイントで工法を判断すればよいのでしょうか?
専門家に相談する
工法選びの素人判断は難しいため、専門家に相談することをおすすめします。建物構造や関連法規、長期耐久力などを考えて工法を提案してくれるでしょう。
簡単1分!無料見積もりフォーム(図面があるとより簡単に入力できます。)
ここでは、各工法のメリットとデメリットをご紹介します。

曳家工法のまとめ
曳家工法の姿曳移動(腰下)工法、基礎共工法、腰付工法についてまとめると次のような形になります。
曳家工法のメリット・デメリット|建物、特徴、期間、費用
姿曳移動工法(下腰工法)
建物 :
木造住宅(主に在来工法の建物)
特徴 :
建物土台下のコンクリート基礎に部分的な穴をあけ、その穴に通した鋼材(下腰)で土台から上部分の建物荷重を上げる工法。
メリット:
- コンクリート基礎を除いた建物本体を傷つける事がなく、費用は比較的安価であること。
- 比較的簡易な資材で建物の移動が可能である。
- 基礎共工法に比べると掘削手間が少ないため、工期が比較的短くなりやすい。
- また、床を剥がすことでさらなる工期短縮が図られるため、工期の厳しい現場には向いている。
- 上げ家時に床下断熱の施工が容易にできる。
- 建物の歪み直し、家起こしなど同時施工が可能である。
デメリット:
- 新設のコンクリート基礎に鋼材(下腰)を落とし込むため、基礎に欠損部ができる。この欠損部には補強筋の配筋や鉄筋同士の継手を行うことで強度の低下を防ぐことができるが、適切な材料、施工法が欠かせないため基礎欠損部の復旧にも十分な知識と経験が必要。
- 床下の仕様次第でアンカーボルトの緊結が難しい場合がある。場合によってはアンカーボルトの緊結のために、壁を壊す必要がある。
- メーカー仕様の大臣認定の建物では基礎コンクリートも認定に含まれることがあるので、適用できない場合がある。
- 他の敷地からの移転においては、「木造2階建て」、「延べ面積200㎡を超える平屋建て」は2025年改正建築基準法の影響を受けて、「新2号建築物」となり、審査省略制度の対象外となります。
※ただし、移転認定を受けたものについてはその限りではありません。
腰下工法のお見積り例
(平成31年 105.1㎡)
曳家 費用 お見積 栃木県 宇都宮市 腰下工法基礎共工法
建物 :
鉄筋コンクリート造、重量鉄骨、ハウスメーカー軽量鉄骨、集合住宅など
特徴 :
建物のコンクリート基礎も建物本体と共に移動する工法です。建物基礎下の地盤を掘削して建物をジャッキアップして移動します。
メリット:
- 基礎も本体も一緒に移動することができるため、荷物などそのままの移動ができる。
- 十分な知識・経験・資材を用いると建物本体に傷をつけることなく移動ができる。
- 建物内部の給排水管を一緒に移動することができるため、設備復旧費の削減につながる。
- 大手メーカーによって建てられた大臣認定の建物でも曳家が可能である。
- 新築時の地震保険や新規の地盤保険など認可される場合が多い。
デメリット:
- 姿曳工法に比べ、比較的に重量が大きくなり、必要な資材がふえるため、工期も伸びる。
- 使用資材や必要人工が増えるため価格も高くなる傾向がある。
- ジャッキアップ時の地盤沈下等のリスクも増えるため専門的な知識やジャッキや敷き鉄板等の資材が必要になり、十分な知識・経験・資材を持たない業者が仕事をするとかえって建物を痛めてしまうことがある。
- 既存基礎が不良施工である場合、補強工事が必要となる。
基礎共工法のお見積り例
(令和5年 127.6㎡)
曳家 費用 見積 宇都宮市 木造二階建腰付移動工法(上腰工法)
建物 :
木造住宅、神社、仏閣
特徴 :
柱もしくは木束に鋼材を金物やワイヤーで緊結し、その鋼材で建物荷重を上げる工法です。主に神社や仏閣のような土台のない建物や土台が腐食してしまっている建物等に用いる2025法です。
メリット:
- 腐食した土台の交換が可能である。
- 歴史的建造物に対する工事が可能である。
- 工期は比較的短くなりやすい。
- 費用も安くなりやすい。
デメリット:
- 柱、木束での緊結は滑りやすいため、充分な知識・経験のある職人でないと工事品質が大きく下がる。
- 一般木造住宅、倉庫では壁を取り壊す必要がある場合がある。
以上、3つの曳家工法について解説をしましたが、どんな工法においても、充分な知識・経験が必要です。例えば、姿曳工法の基礎の欠損部は鉄筋が非連続になってしまうというデメリットがあるのですが、鉄筋構造に補強筋を用いたり、機械式継手を用いることで、デメリットを軽減することができるのです。つまり、同じ工法でも業者によってデメリットの軽減方法が違うため、御見積書を受け取った際にはたくさんの疑問点・不安点を質問して、どんな業者かを見極めることが大切です。
簡単1分!無料見積もりフォーム(図面があるとより簡単に入力できます。)
その他五月女建設の施工事例
 ※工法や費用の事例を紹介しています。
※工法や費用の事例を紹介しています。
なぜ十分な現地調査を必要性があるのか?
曳家工事において十分な現地調査が必要な理由は、安全性の確保、効率的な工事計画の立案、リスク管理、そしてコスト管理など、多岐にわたります。
安全性の確保
安全性の確保が最も重要です。現地調査を通じて、建物の構造的特性や状態、周囲の地盤条件を正確に把握することができます。これにより、建物を安全に持ち上げ、移動させるための適切な方法を決定できます。例えば、地盤が不安定であったり、地下水位が高い場合、液状化現象などのリスクが高まるため、それに応じた対策を講じる必要があります。
つまり、工法の違いによって生まれるリスクから安全性を確保するには十分な現地調査が必要になるのです。
効率的な工事計画の立案
効率的な工事計画の立案が可能になります。現地調査で得られた情報を基に、必要な補強作業や適切な移動方法を決定できます。例えば、建物の重心や基礎の強度、過去の修繕履歴などの情報は、工事の計画段階で非常に重要です。
工法の違いによってまるで変ってしまう工事作業内容を効率的に行うためにも現地調査が必要になります。
リスク管理
リスク管理の観点からも、現地調査は不可欠です。建物の移動中には様々なリスクが伴いますが、事前に周囲の状況を把握しておくことで、それらのリスクを軽減することが可能です。例えば、建物周囲の工事支障物や地盤の状況を確認することで、工事中のトラブルを未然に防ぐことができます。
工法の違いによって変わる建物の重量、必要な地耐力、資材の量も現地調査をすることで、リスク管理ができるのです。
また選ぶ工法によっては地盤保証が失われたり、メーカー保証の引き継ぎができなくなる場合もあるため、その違いのわかる曳家業者への相談が大切です。
つまり、作業面だけではなく、作業が完了したあとの生活にかかわるリスク管理が必要になります。
コスト管理
コスト管理の面でも現地調査は重要です。調査によって得られた情報は、曳家工事の費用見積もりに直結します。例えば、移動距離や必要な施工方法が明確になることで、予算を適切に設定できるようになります。また曳家工事では、工法によって生まれるデメリットを回避するために、様々な作業が必要になりますが、このような情報を事前に把握しておくことで、不必要なコストを避けることができます。
またコスト管理においてはライフサイクルコストの
法的および規制上の要件
法的および規制上の要件を満たすためにも現地調査は重要です。多くの場合、曳家工事には地方自治体や関連機関からの許可が必要であり、これらの許可を取得するためには詳細な調査結果を基にした報告書が求められることがあります。工法によっては、法的な観点から条件を満たさないものもあるため、現地調査、図面などの精査により工法を決定する必要があるのです。
信頼関係の構築
現地調査はお客様との信頼関係を築く上でも重要な役割を果たします。専門的な調査とその結果に基づく透明性のある説明は、顧客の不安を軽減し、信頼感を高める要素となります。どの工法を選ぶのか?なぜその工法を選択するのか?メリット・デメリットは何なのか?をしっかり質問し、理解することで工事が終わってからも長年続く信頼関係を構築することができるのです。
以上の理由から、曳家工事における十分な現地調査は、安全性、効率性、リスク管理、コスト管理、法的要件の遵守、そして顧客との信頼関係構築など、多くの面で不可欠な役割を果たしています。適切な現地調査を行うことで、より安全かつ効率的な曳家工事が実現され、顧客満足度の向上にもつながるのです。
また工法選びはお客様の想いを残す曳家工事を行う際にはとても重要な要素です。だからこそ工法の特徴を知り、そのメリット、デメリットを理解することで損することのない安心安全かつお客様のニーズに最適な工事を行うことができます。
信頼できる専門家を探し、十分な現地調査を行うことで、しっかり納得の上で、適切な工法を見つけてください。
【曳家工事】工法に関するQ&A
Q1: 曳家工事を選ぶ主な理由は何ですか?
A1: 曳家工事を選ぶ主な理由は、建物の保存と移動(思い出や歴史的価値をそのままにできる)、コスト効果(新築の約1/3~2/3程度の費用で済むことが多く、建築資材高騰の影響を受けにくい)、工期の短縮(通常1~2ヶ月程度で完了)の3点です。
Q2: 曳家工事の工法を選ぶ上で何が重要ですか?
A2: 工法によって工事品質、工事後の耐久性、工事価格などが大きく異なるため、工法選びが非常に重要です。建物の構造や建築基準法への対応、そして各工法のメリット・デメリットを知ることが大切です。
Q3: 曳家工法にはどのような種類がありますか?
A3: 主に以下の3つの工法があります。
- 姿曳移動工法(下腰工法)
- 基礎共工法
- 腰付移動工法(上腰工法)
Q4: 姿曳移動工法(下腰工法)はどのような建物に適していますか?
A4: 姿曳移動工法(下腰工法)は主に木造住宅(在来工法の建物)に適しています。
Q5: 姿曳移動工法(下腰工法)の主なデメリットは何ですか?
A5: 新設のコンクリート基礎に鋼材を落とし込むため、基礎に欠損部ができる点、アンカーと土台の接続の難しさが主なデメリットです。この欠損部の補強には十分な知識と経験が必要です。
Q6: 基礎共工法はどのような建物に適していますか?
A6: 基礎共工法は鉄筋コンクリート造、重量鉄骨、ハウスメーカー軽量鉄骨、集合住宅など、基礎も一緒に移動する必要がある建物に適しています。
Q7: 基礎共工法のメリットは何ですか?
A7: 基礎共工法のメリットは、基礎も本体も一緒に移動できるため荷物などそのまま移動でき、建物本体に傷をつけにくい、建物内部の給排水管を一緒に移動できるため設備復旧費の削減につながる、大臣認定の建物でも曳家が可能である点などです。
Q8: 腰付移動工法(上腰工法)はどのような建物に適していますか?
A8: 腰付移動工法(上腰工法)は、木造住宅、神社、仏閣など、柱や木束に鋼材を緊結する工法で、特に土台のない建物や土台が腐食している建物に用いられます。
Q9: 曳家工事において十分な現地調査が必要な理由は何ですか?
A9: 十分な現地調査が必要な理由は多岐にわたりますが、主に安全性の確保、効率的な工事計画の立案、リスク管理、コスト管理、法的および規制上の要件の遵守、そして顧客との信頼関係の構築のためです。
Q10: 同じ工法でも業者によってデメリットの軽減方法が違うのはなぜですか?
A10: 同じ工法でも、業者が持つ知識や経験、使用する材料、施工方法によってデメリットの軽減方法が異なります。例えば、姿曳工法の基礎の欠損部に対して、補強筋や機械式継手を用いるなど、業者によって技術的なアプローチが異なるためです。
ーーー
まとめ|想い出が未来につながる工法を選ぶ
私たちのような建物を残す曳家工事をしていると会う人によって「新しい家のがいいよ」と笑われることもあります。
ですが私たちは「建物だけでなく想いも曳く」という心構えのもと曳家工事に取り組んでいます。
なぜなら「想い」とは今までたくさんたくさんお客様がご家族を愛してきた想い。たくさんの想い出の積み重ね。嬉しい思い出、悲しい思い出、人生初めての大きなローンを組んだ時の恐怖・興奮の思い出や子供の成長が刻まれた家、空間。家族会議で人生で最も大きな決断をした部屋、大きな声でケンカした場所。
そんな大切な大切な想い出も共に曳かせて頂くのが私たちの本懐です。
私たちは一緒に働く仲間の人生の価値を最大にしたい。だからこそそのためにも私たちが関わるお客様の人生の価値を最大にしたい。
そんな想いで仕事をしています。
ーーー
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
曳家に関する法律の第三者的なアドバイスが欲しい方、不明な点等ある方などありましたら、日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女がお答えします。ぜひ曳家先生へのウェブ相談、もしくは五月女建設のお問合せフォームでご連絡くださいね。あなたの身に寄り添った立場で協力させて頂きます。
出典
「曳家業務 曳家のガイドブック基礎知識」(一般社団法人日本曳家協会)
「家が動く!曳家の仕事」(一般社団法人日本曳家協会)