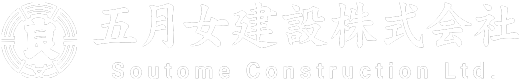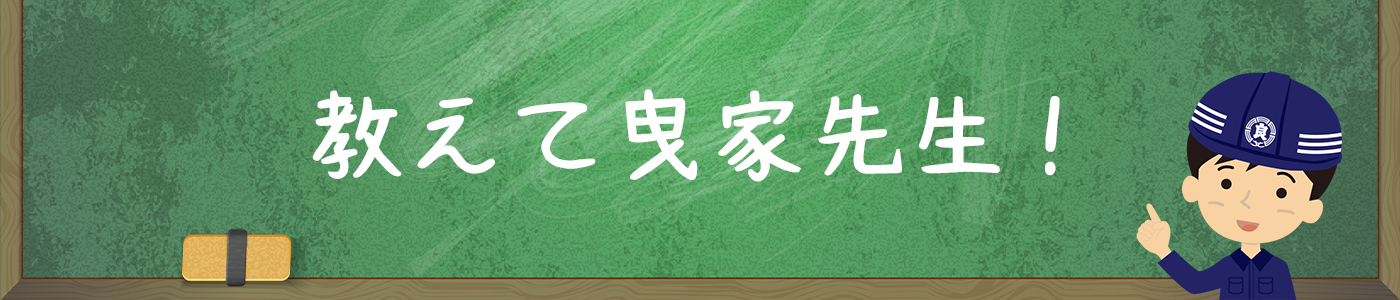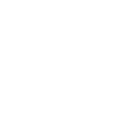【北関東版】失敗しない!曳家費用の相場と補償金を徹底解説!|曳家見積もり前に
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! ~絶対に損しない曳家費用のコツ~ 相場や補償金まで徹底解説!
こんにちは曳家先生です。前回は、「絶対に損しない曳家のコツ」についてお話ししました。第二話は「絶対に損しない曳家費用のコツ」です。
「区画整理で立ち退き…新築と曳家、どっちが良いんだろう?」 「大切な家を移動したいけれど、曳家工事ってどれくらい費用がかかるんだろう?」 「見積もりを取る前に、費用の相場や内訳を知っておきたい…」そんなモヤモヤを抱えていませんか?
この記事では、北関東エリアで曳家をご検討中の皆さまを対象に曳家工事にかかる費用の全体像から内訳、北関東エリアでの相場、費用を賢く抑えるコツ、そして新築と曳家の費用の比較まで、専門業者の視点から分かりやすく解説します。
さあ、最後まで読んで、確かな一歩を踏み出しましょう!
まずは知っておこう!曳家工事にかかる費用の種類と目安
曳家工事全体の費用は、単に建物を移動させるだけでなく、様々な付帯工事費用が含まれます。まずは、どのような費用がかかるのか、その種類と一般的な目安を見ていきましょう。

- 解体処分費用(約20万円~):建物と一緒にあるいらない構造物や移植をしない庭木、塀や駐車場などを解体し、処分する費用です。
- 曳家工事費用(約300万円~):建物を移動するための費用です。建物の構造によって工法を選択するため、一概に大きさだけでは判断ができないこともあります。また、業者によってもどのくらいの工事品質で建物を移動するかによって大きな違いがでます。
- 設備工事費用(約120万円~):建物を移動する際には、電気・ガス・水道・下水など再接続が必要なことがあります。この費用には元々の配管撤去費用や新規配管費用、それに伴う各種手続き費用が含まれます。
- リフォーム工事費用(約20万円~):建物を移動する際に、水回りや壁紙、電気などを交換する場合の費用です。建物の工法や施主さんの希望によっては全く必要のない場合があります。
- 外構工事費用(約40万円~):建物を移動して、駐車場や塀、倉庫、外の水道など生活に必要なお庭を作る費用です。
- 建築確認申請費用(約50万円~):曳家工事は建築基準法(法2条13号)において「移転」もしくは「新築(曳移転)」に該当する建築行為に定義されています。そのため、一定の例外を除いて、建築確認申請が必要となるため、その費用が必要になります。
- 地盤調査・地盤改良費(約5万円~):建物を移動した後、長く安全に住み続けるためには強固で安定した地盤の上に建物を移動する必要があります。そのために工事前の地盤調査とその結果によっては地盤改良費費用が必要になることがあります。
- その他費用:
- 曳家工事を始める前に引っ越し費用やアパートの家賃など様々な費用がかかることがあります。
- 技術を伴わない曳家業者だと本来必要のない外壁や壁紙などの補修費用が生じることもあります。
- 業者が損害賠償保険に加入しているかどうかをきちんと確かめましょう。
【具体的な費用イメージ(例)】
一般的な木造2階建て住宅(延床面積 約125㎡ / 約38坪)を20メートル移動させる場合、曳家工事そのものの費用相場は約500万円程度と言われています。たただし、これはあくまで曳家工事単体の目安です。 上記の解体、設備、基礎、外構などの付帯工事費用が別途必要になります。
「もっと詳しく知りたい!」、「我が家の場合は!?」、「実際の御見積の内容を見てみたい!」と言う方は、「教えて曳家先生 第十三話~絶対に損しない坪単価のコツ~」を参考にして下さい。
お客様に実際にお渡しした見積もり金額をもとに参考坪単価を算出しています。
それでは、費用の種類とは別にどんな要因が曳家の費用に影響を与えるのでしょうか?
次にその主な要因について解説していきます。
なぜ変動する?曳家費用に影響を与える9つの要因:
同じような家でも、曳家費用が変わってくるのはなぜでしょうか?費用に影響を与える主な要因を知っておきましょう。
- 建物の構造とデザイン:重い構造(鉄筋コンクリート造)や複雑な形状の建物ほど費用が高くなります。例えば、長方形に近い形の建物に比べ、L型の建物だと、最大奥行きと最大間口の長さが同じだった場合、長方形の方が面積が大きいにも関わらず、費用には大きな違いが出にくくなります。
- 移動距離と地形:距離が長いほど、方向転換が多いほど、また高低差が高いほど、地形が複雑なほど費用が上がります。距離・方向転換・高低差は大きいほどに、枕木やレールなどの資材が多く必要になるため、その損耗費や運搬費用が多くかかるようになります。また、地盤が緩やかな場所の上を建物が移動する場合、必要な地耐力を確保する必要があるため、敷鉄板や地盤改良など別途行う場合はその費用も必要になります。
- 既存基礎と新設基礎の位置の重複:基礎が重複する場合、新設する基礎の一部が既存の基礎と重なるため、その部分の基礎工事は、建物を持ち上げた状態での狭い場所での作業をとなり、機械施工が困難になります。 そのため、重複部分の基礎工事費は、人力施工単価の比率が増え、その分割高となります。
- 建築付随工作物の有無:建物の屋根に設置されているアルミ製の物干し台やサンルームなどがあると、その分の面積が増えるため、費用が追加されることがあります。
- 規模補正率と2階建補正:曳家基本工事費は平家建物を基本として算出されており、1階床面積に応じて補正されます。 これは、床面積が大きくなるほど、曳家作業に必要な資材や労力が増加するためです。また、階建の建物は、平家建物に比べて建物重量が大きいため、仮受け材や安全対策にかかる費用などが追加で必要となります。このため、2階建補正率を乗じることで、2階建ての建物に必要な追加費用を反映しています。

- 撤去できない支障物、事前調査で発見できなかった地中埋設物:撤去することができない塀、庭石、庭木、工作物、電線など曳家工事に際しての支障物があると、その対策の為の費用が別途かかることがあります。また、お客様が知る知らないに関わらず、地中埋設物が出てきた場合にはその撤去・処分費用が追加になることがあります。この場合、機械が入らない狭所作業だと、撤去に要した人力施工単価が追加になります。
- 建材や人件費の市場価格:2021以降、世界的な原材料の品薄・高騰の影響により、日本の建設業においても価格の高騰が発生しています。また建設業労働市場の人材不足の影響を受けて、資材価格の高騰だけではなく労務単価も全職種単純平均で約16%上昇しているため、これらの価格が曳家の費用に転嫁されることになります。
- 地域性:地域によって人件費や資材費が異なるため、価格に差が出ます。特に施工会社からの距離が一定以上になると、別途宿泊費や長距離運搬費(高速代)などが追加されるため、費用が上がっていきます。
- 付帯工事:基礎工事や設備の再設置、外構工事やリフォーム工事など、追加で必要な工事によってコストが増加します。他にも施工品質の良くない業者の工事には別途補修費用が必要になることがあり、望む望まないに関わらず、費用が加算されることがあります。
意外に無視できない2025年建築基準法改正の影響
改正建築基準法により、新築木造住宅の費用は約7.5%上昇する見込みです。例えば、一般的な木造住宅(延床面積約120㎡程度)を新築するのに改正前の費用が約4,985万円の場合、改正後は約5,359万円になります。
主なコスト増の要因は、省エネ基準適合義務化(高性能断熱材・設備の採用、設計負荷増)と、4号特例縮小による構造基準の見直し(構造計算書の提出義務化、関連費用増)です。
また、許認可プロセスの複雑化によるリードタイム長期化も、間接的なコスト増につながる可能性があります。
関連記事:
【2025年4月版】曳家での建築確認のコツ!建築基準法・既存不適格など曳家先生が解説!
曳家 vs 建て替え コストを比較!どっちがお得?:

※曳家費用(総プロジェクト費)には、キッチン・風呂・トイレ・壁紙・外壁塗替えなどリフォーム費用、駐車場や庭の外構費用、建築確認申請費用、その他費用など、曳家工事にかかるすべての費用を想定しています。
※<建築士様、曳家業者様、他業者様>この図を使用する際は五月女建設までご連絡、本記事のリンクを添付の上ご使用ください。
曳家は一般的に建て替えよりも安価です。例えば、曳家工事だけで比べると新築の半額以下。曳家工事の費用はそのすべての工事費用を含めても、新築の約6割から7割程度になることが多いです。ただし、2021以降、円安の影響により建設資材の高騰が続いており、全職種単純平均が約16%上昇に対し、資材高騰が80%もあることを考えると、曳家工事では新築工事に比べ新規材料を使う機会がすくないことから、2025年現在だと曳家工事の工事費用のほうが更に割安になる傾向があります。
一方、建て替えの場合は、新築住宅を建設するための全体的なコストが高額になります。土地代や設計費用、建材費、人件費などが含まれ、さらなる建設資材の高騰、労務単価の上昇により、2019年の新築費用を比べると3割り程度高騰していることから、実際に見積もりを取ってみると予想よりも大きな金額になることも珍しくありません。
| ウッドショック前 | 2025年 | 2025年建築基準法改正後 | |
|---|---|---|---|
| 曳家費用 (総プロジェクト費用) | 約2,418万円 | 約3,143万円 | 約3,300万円 |
| 新築費用 (本体+付帯工事費) | 約3,720万円 | 約4,985万円 | 約5,359万円 |
| 曳家費用 対 新築費用 比率 | 65.0% | 63.1% | 61.6% |
※一般的な木造住宅(延床面積約120㎡程度)、フラット35のデータ、建物移転算定要領、五月女建設積算データより算出

※曳家費用(総プロジェクト費)には、キッチン・風呂・トイレ・壁紙・外壁塗替えなどリフォーム費用、駐車場や庭の外構費用、建築確認申請費用、その他費用など、曳家工事にかかるすべての費用を想定しています。
※20025年の改正建築基準法による費用上昇率は、新築で約7.5%、曳家で約5.0%と推定されます。
※これらの数値はあくまで改正前推定費用に基づいた試算であり、個別の案件によって実際の費用は大きく変動する場合があります。
特に曳家費用について:
- 曳家費用は、以下の要因によって大きく左右されます。
- 建物の状態(構造、大きさ、築年数など)
- 移動する距離や経路の条件
- 基礎工事の内容
- 選択する専門業者
- なお、大規模なリフォームや外構工事などを伴わない場合、曳家費用は比較的さらに抑えられる傾向にあります。
また工事後の固定資産税についても大きな差が生まれます。詳しくは自治体の担当部署までお問い合わせください。
曳家か建て替えのコスト比較には、曳家、新築含め、いくつかの業者に見積を取ることが大切です。
無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。
公共事業の場合は?曳家補償金の算定方法?
それでは区画整理や道路拡張にかかる曳家の補償金はどのように作成されているのでしょうか?実は、日本の国土交通省が作成した「曳家移転料算定要領」により、木造住宅を対象にした曳家移転料の算定方法について、具体的な事例を交えながら詳細に解説され、それをもとに補償金が算定されています。
特に、曳家の種類、施工手順、移転料の算定方法、基礎工事、建築設備工事、建物附随工作物工事、共通仮設費、諸経費、廃材運搬費、その他について、わかりやすく説明されているのが特徴です。また同書には「木造建物以外の建物や、構造が異なる建物は、専門メーカー等の見積を徴収する」とあり、鉄骨造倉庫や鉄筋コンクリート造建築物、石造蔵などの建築物の補償金算定には信頼ある曳家業者の見積もりが反映されているのです。
それでも安く、安心・安全に曳家をしたい!|曳家の費用を抑えるコツ:
それでも安く、安心・安全に曳家をしたいですよね。
実は曳家の費用を抑えるコツにはいくつかのコツがあるのです。
曳家は 専門的な工事なので、業者によって費用やサービス内容が大きく異なります。
そのため、複数の業者から見積もりを取り、しっかりと比較検討することが重要です。
では、曳家の費用を抑えるためには、具体的にどんなポイントに気を付ければ良いのでしょうか?
コツ①複数の業者から見積もりを取る
少なくとも3社以上の曳家業者から見積もりを取りましょう。
その際には、単に金額だけでなく、以下の点もチェックしましょう。
工事費用:内訳まで詳しく確認し、不明点があれば質問する。特に、2025年建築基準法改正について、移転認定による制限緩和、既存不適格など、どの程度知見があるかによって、移転工事にかかる費用が変わってしまいます。
施工実績:実績豊富な業者ほど、安心感があります。特に、過去に 似たようなな建物の曳家実績があれば、より安心です。
施工品質:工事の丁寧さ、仕上がりの美しさなども考慮しましょう。ホームページやパンフレットで過去の事例を見てみましょう。
保証内容:万が一のトラブルに備え、保証内容も確認しておきましょう。
アフターサービス:曳家後のサポート 体制も大切です。
担当者の対応:親切丁寧な対応で、信頼できる担当者かどうか見極めましょう。また見積書を預かった際に、費用についての不明点が解消できるように質問をしましょう。
コツ②解体・設備工事などはよく知る業者に相談する
曳家と同時に、解体工事や設備工事が必要になるケースも多いでしょう。
もし、信頼できる工務店や設備業者とお付き合いがあれば、相談してみるのも良いでしょう。
すでに 関係性ある業者なら、融通をきかせてくれるかもしれませんし、費用を抑えられる可能性もあります。
コツ③最も重要!業者の「技術力」と「想い」を見極める
実は、曳家費用を抑える上で見落としがちなのが「曳家後の補修費用」です。
曳家業者の技術力によって、建物の損傷状況は大きく変わります。
技術力の高い業者は、建物を丁寧に扱い、建物の損傷を最小限に抑えるため、結果的に補修費用も抑えられます。
では、曳家業者の技術力を見極めるにはどうすれば良いのでしょうか?
- 会社の歴史を調べる:長年の実績を持つ会社は、それだけ技術力も高いと考えられます。
- 保有資格や工法 を確認する:曳家に関する十分な資格や資材・技術を保有しているか確認しましょう。
- 施工事例を詳しく見る:どのような建物を、どのように曳家したのか、具体的な事例をチェックしましょう。最近ではホームページに事例を掲載していることもあるのでチェックが必要です。

例)五月女建設の施工事例
※工法や費用の事例を紹介しています。
- 口コミを参考にする:インターネットや近所の口コミで評判を調べてみましょう。
そして、最も重要なのは、 その曳家業者が「どんな思い」、「どんな誇り」を持って仕事に取り組んでいるか を感じ取ることです。
建物は、そこに住む人にとってかけがえのないものです。
曳家業者もまた、その思いを理解し、責任感と誇りを持って仕事に取り組んでくれるはずです。
参考記事:【曳家の業者選び】評判・口コミで選ぶ優良会社|選び方のコツも解説【チェックシート付き】
【参考】曳家工事の見積り例(五月女建設の場合)
さて、それでは待ちに待ったお見積りの例を紹介します。
処分費や設備工事費など、曳家工事に関連した費用も載せていますので、ぜひ参考になれば嬉しいです。
※コチラは実際に五月女建設でお見積りを出した実例ではありますが、年代、面積や曳く距離、工事内容が違いますのであくまで参考としてください。
(2020年(令和2年)以降材料価格の高騰があります)
【見積もり例1:腰下工法(基礎を新設する場合)】
建物: 木造2階建て(平成31年 / 105.1㎡)
曳家 費用 お見積 栃木県 宇都宮市 腰下工法
【見積もり例2:腰下工法(基礎を新設する場合)】
建物: 木造2階建て(令和4年/84.9㎡)
曳家工事 見積もり 木造二階建て 下腰工法
【見積もり例3:基礎共工法(基礎ごと移動する場合)】
建物: 木造2階建て(令和5年 / 127.6㎡)
曳家 費用 見積 宇都宮市 木造二階建
相談だけでも大歓迎です。あなたの家の曳家費用はいくらになるか無料で確認できます。
まず概算費用を調べてみる
【よくある質問~曳家費用のQ&A~】

Q1. 曳家工事の費用目安は?
A1.付帯工事費込で新築費用の4~7割程度が目安です。ただし、状況により大きく変動するため、信頼ある曳家業者へお問合せください。
Q2. 曳家工事の費用には何が含まれる?
A2. 主に、曳家工事費、解体、設備、リフォーム、外構、建築確認申請、地盤調査・改良費などです。引っ越し代なども考慮が必要です。
Q3. 曳家費用が変わる要因は?
A3. 建物の構造・デザイン、移動距離・地形、基礎の重複、付随工作物、規模・階数、支障物・埋設物、市場価格、地域性、付帯工事の内容・品質などです。
Q4. 曳家と建て替え、どっちがお得?
A4. 曳家がお得です!一般的に曳家の方が安価(新築の6~7割程度)です。近年の資材高騰でさらに割安傾向。固定資産税も安くなる可能性があります。比較検討が重要です。
Q5. 曳家費用を安く抑えるコツは?
A5. ①複数業者から見積もり比較、②解体・設備は知人業者へ相談、③技術力と想いのある業者選び(重要)の3点です。
さらにご興味のある方は下の記事を参考ください。
参考記事:曳家の業者選び? 会社の専門性によるリスクや選び方を徹底解説!
Q6. 公共事業での曳家補償金はどう決まる?
A6. 国土交通省の「曳家移転料算定要領」に基づき算定されます。木造以外は専門業者の見積もりが参考にされます。
Q7. 五月女建設の見積もり例は見れる?
A7. 記事内に参考として2例(腰下工法、基礎共工法)掲載されています。ご参考ください。実際見積もりをご希望の際には見積フォームからお問い合わせください。
Q8. 曳家検討、何から相談すればいい?
A8. まずはお住まいの建物が施工上、法律上、曳家をできるかを調べることが重要です。他に現時点でご不安な点などどんな小さなことでもまずご相談ください。概算費用はウェブサイトの「簡単見積もり」、直接相談は「ウェブ相談」か電話(0289-62-8235)で曳家先生こと五月女へ。もちろん相談だけでもOKです。
Q9. 工事中に家が壊れたら?保険はある?
A9. 業者を選ぶ際はその業者の技術力や損害賠償保険への加入を必ず確認してください。技術力の高い業者ならリスクも低減できます。
Q10. 見積もり以外に追加費用は発生する?
A10. 予期せぬ地中埋設物や支障物の撤去費用などで発生する可能性があります。技術力が低いと不要な補修費がかかることも。五月女建設はお客様の納得のない追加請求はしない方針です。
ーーー
曳家と費用のまとめ:納得のいく曳家工事のために
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
今回は、曳家工事の費用について、その内訳から相場、費用を抑えるコツまで詳しく解説しました。
曳家費用は様々な要因で変動しますが、事前に知識を得て、信頼できる業者を選ぶことで、適正な価格かつ安心できる工事をすることができます。
ーーー
お客様との会話:新築と曳家について
私たち五月女建設と曳家工事のご契約を頂いたあるお客さんの話です。
お客様:「五月女さん、子供たちから『こんな寒い家住んじゃだめだよ。今の家はもっとあったかいんだから、小さくていいから暖かい建物に住みなさい』って、子供に怒られちゃったんですよ。でも私はこの家住みたいと思ってるんだよね。これって私のわがままかしら?」
五月女:「立場の違いがあるから、確かにお子さんたちはこっちの新しい家に住むことおすすめするかもしれないですよね。でも曳家するかどうか悩まれる方はみんな、なぜ悩まれるか?・・・やっぱりこの家にはたくさんたくさん大切な思いが詰まってるからだと思うんです。それにお盆屋正月かもだけかもしれないけれど、やっぱり実家があるからこそお子さんやお孫さんたちが集まる。その想い出や絆がたくさんたくさん刻まれた場所を守る。これが私たちの仕事です。もしこれがお客様のわがままなら、そのわがままを叶えることが私たちの仕事なんです。」
お客様:「そうだよね。やっぱり悩むけど、五月女さんこの後もよろしくね。」
五月女:「もちろんです!こちらこそよろしくお願いします。」
ーーー
私たちも「できるだけ安く届けたい」という思いと、「30年後も安心できる嘘のない工事をしたい」という思いを持って、お客様のお気持ちに添った価格の設定を行っています。
私たちが曳家工事の費用を抑えるための工夫
- 経験豊富なスタッフによる効率的な施工
- 建物の状況に合わせた適正な資材・工法の選定
- お客様のご要望に寄り添ったたプランニング
を常に心がけ、適正価格での曳家工事をご提供できるよう努めています。もちろん、見積もりは詳細かつ明瞭にし、ご納得いただけない追加料金は一切いただきません。
「まだ不安なことがある」「うちの場合は具体的にいくら?」など、疑問やご心配事がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。「曳家先生」こと日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女が直接お話を伺います。
地元の気候・地盤を知り尽くした私たちだからこそ、最適な施工が可能です。
「大切な家を守り、ご家族の想いを未来へ繋ぐ」
その手伝いを、ぜひ私たちにさせてください。
参考文献
・曳家業務 曳家のガイドブック基礎知識(一般社団法人日本曳家協会)
・建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い建設資材高騰・労務費の上昇等の現状(日本建設業連合会)
修正:2025月3月5日