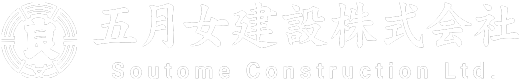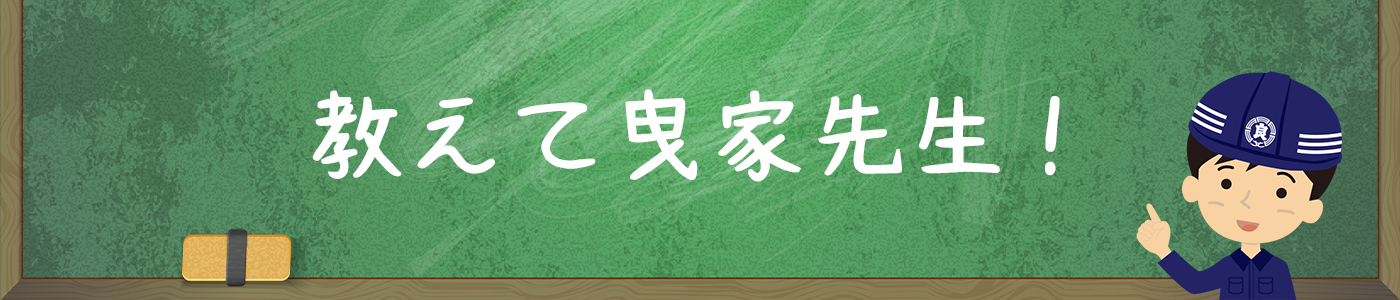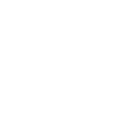宇都宮で大谷石建築の未来を紡ぐ!五月女建設の曳家・改修技術と大谷石の魅力
公開日: 最終更新日:
宇都宮で大谷石建築の未来を紡ぐ!五月女建設の曳家・改修技術と大谷石の魅力
栃木県、特に宇都宮エリアで愛され続ける「大谷石(おおやいし)」。その独特の風合いを持つ蔵や建築物は、地域の美しい景観を形作る大切な財産です。しかし、時間の経過と共に、改修や移転の必要性に直面することも少なくありません。
「うちの大谷石の蔵も、そろそろ専門家に見てもらった方がいいのかな?」 「この歴史ある建物を、安全に、そして価値を損なわずに次の世代へ引き継ぎたいけれど、どうすれば…」 「曳家(ひきや)って聞くけど、うちの建物でも本当にできるの?費用は?」
そんな想いを抱える皆様へ。私たち五月女建設は、明治35年(1902年)の創業以来、120年以上にわたり、栃木県を中心に曳家工事をはじめとする建設工事に携わり、特に大谷石建築の保存・活用に情熱を注いできました 。
この記事では、大谷石建築の曳家・改修をお考えの皆様が抱える疑問や不安を解消し、大切な建物を未来へ繋ぐためのお手伝いができれば幸いです。五月女建設が手掛けた具体的な曳家事例から、大谷石そのものの魅力、改修や移転に関わる法律の話、そして地域を挙げて大谷石文化を盛り上げるイベントまで、幅広くご紹介します。
五月女建設の曳家・大谷石専門性:実績が語る信頼
建物をそのままの形で移動させる「曳家」は、高度な技術と豊富な経験が求められる専門分野です。五月女建設は、この曳家工事を事業の中核に据え、数々の歴史的建造物の保全に貢献してまいりました 。
事例紹介1:楠様邸 大谷石蔵の曳家 – 記憶を未来へつなぐ仕事
宇都宮市鶴田第二土地区画整理事業に伴い、昭和37年建造の楠様邸大谷石蔵の移転が必要となりました。この石蔵は、所有者である楠様ご自身も石を担いで建造に関わったという、深い愛着と歴史が刻まれた建物です 。
- プロジェクトの概要:
- 対象:大谷石造2階建て石蔵(重量約90トン)
- 移動距離:約170メートル
- 回転角度:185度
- 高低差:2.6メートル
- 特記事項:道路横断、畑地横断を含む複雑な工事
- 採用技術と工夫:
- 専門的な曳家工法である「下家工」を採用。
- 畑地横断に際しては、地盤の安定化のため「敷鉄板+表層改良」を実施 。
- 成果と評価: この難易度の高い曳家工事は無事完了し、その成果は宇都宮市発行の「大谷石建造物の保全・活用に向けた解説集」にも事例として紹介されるなど、公的にも高く評価されています 。大切な思い出の詰まった建物を、安全かつ確実に未来へと引き継ぐことができました。
曳家 栃木県宇都宮市|施工事例|区画整理 楠様邸 大谷石蔵
事例紹介2:S様邸大谷石蔵の曳家 – 日本遺産景観保護への貢献
宇都宮市の道路拡張事業に伴い、大谷地区にある大谷石蔵の移転工事が必要になりました。
「施主様は道路が広がったら、敷地内に建物が収まらないんじゃないか」とお悩みでした。
大谷地区は近年日本遺産の認定もされたことから、今となっては貴重な大谷石蔵の保存は価値ある仕事となりました。
文化財の曳家は、単に建物を移動させるだけでなく、その歴史的価値を一切損なうことなく次世代へ継承するという、極めて高度な技術と細心の注意が求められます。五月女建設は、このような重要なプロジェクトにも携わらせていただくことで、文化財保護の一翼を担っています。
曳家だけではない、大谷石建築のトータルサポート
五月女建設の専門性は曳家工事に留まりません。大谷石建築を長期的に維持・活用していくためには、建物の状態に応じた様々な対応が必要です。
- 構造補強: 曳家工事の際に、湿気や虫害で傷んだ土台や柱を交換し、建物の構造を強化することが可能です 。
- 免震工事: 地震の多い日本において、貴重な大谷石建築を揺れから守る免震工事も、専門企業THK社と協力して行っています 。当社の曳家工法を用いた免震改修工事は、栃木県の経営革新計画にも認定されています 。
- 沈下修正・嵩上げ工事: 建物の傾きを修正したり、浸水被害を防ぐために基礎や地盤を嵩上げする工事も実績があります 。これにより、建物の耐久性向上にも貢献します。
私たちは、大谷石建築が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案できる「文化遺産保護のパートナー」として、皆様の大切な資産をお守りします。
無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。
大谷石の魅力再発見:あなたの知らない可能性
独特の温かい風合いで人々を魅了する大谷石。その魅力は見た目だけではありません。ここでは、知られざる大谷石の力をご紹介します。
大谷石とは? – 宇都宮が誇る唯一無二の自然石
大谷石は、栃木県宇都宮市大谷町付近でのみ採掘される軽石凝灰岩です 。約2300万年前の火山活動によって生まれたと考えられ、世界でもこの地域でしか産出されない、まさに「唯一無二」の貴重な石材なのです 。
- 美的魅力:
- ミソ: 大谷石の表面に見られる茶褐色の斑点模様「ミソ」は、石が生成される過程で自然に生まれるもので、一つとして同じものはありません 。このミソの大きさや分布によって、「細目(さいめ)」「中目(ちゅうめ)」「荒目(あらめ)」といった等級に分けられます 。
-
- 温かみのある風合い: 素朴で落ち着いた色合いと、手触りの良さが、和洋問わず様々な建築デザインに調和します 。
- 加工のしやすさ: 比較的柔らかく加工しやすいため、古くから建材や彫刻などに利用されてきました 。フランク・ロイド・ライト設計の旧帝国ホテルや、カトリック松が峰教会など、歴史的建造物にも使用されています 。
- 驚きの機能性:
- 耐火性: 1000℃以上の高温にも耐える優れた耐火性を持ち、古くからかまどや暖炉などに利用されてきました 。
- 調湿効果: 大谷石に含まれる天然ゼオライトの多孔質な構造が湿度を調整し、夏は涼しく冬は暖かい、快適な室内環境を保ちます 。古くは米の貯蔵倉庫の材料としても活用されました。
-
- 遠赤外線効果: 遠赤外線を放射し、空間の快適性を高めたり、食材の風味を引き立てたりする効果があると言われています 。
- 吸音・音響効果: 音を吸収しやすく、レコーディングスタジオやオーディオルームにも採用されるほど優れた音響効果を発揮します 。今でも宇都宮市内では大谷石を活かしたイベントが人気を博しています。
- 消臭効果: ゼオライト成分がガスや水分を吸着し、気になる臭いを抑える効果が期待できます。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの除去能力も高いとされています 。
- 熟成効果: 食品の鮮度を保ちながら熟成を進める効果があり、大谷石の地下空間で熟成された生ハムは旨味成分が増すという報告もあります 。
大谷石の課題と専門家による対策
多くの魅力を持つ大谷石ですが、その特性ゆえの課題も存在します。
- 風化・劣化: 屋外で使用する場合、雨風による浸食や表面の剥離が起こりやすい性質があります。特に「ミソ」の部分は劣化しやすい傾向にあります 。
- 変色: 採掘直後の青緑がかった色から、乾燥や酸化により白っぽく、さらに茶色っぽく変色することがあります 。
- 吸水性とカビ: 吸水性が高いため、雨水などが浸透しやすく、基礎部分などに使用される大谷石はカビの原因となることがあります 。
- 構造的制約: 現行の建築基準法では、大谷石造は「組積造」とされ、大谷石単独では擁壁などの構造部材としての強度が不足すると判断される場合があります 。
これらの課題に対し、五月女建設では、風化防止剤の塗布や適切な補修・補強技術など、専門的な知識と経験に基づいた対策をご提案し、大切な大谷石建築を長く美しく保つお手伝いをいたします。
大谷石建築の改修・移転:知っておくべき法的知識とガイドライン
大谷石建築の改修や移転を検討する際には、建築基準法をはじめとする法規制への理解と対応が不可欠です。
建築基準法との関連 – 既存不適格建築物とは?
多くの場合、古い時代に建てられた大谷石建築は、現行の建築基準法が施行される前に建てられた「既存不適格建築物」に該当します。これらの建物を改修したり移転したりする場合、原則として現行法規に適合させる必要がありますが、一定の条件下で緩和措置が適用されることもあります 。
宇都宮市が発行する「大谷石建造物の保全・活用に向けた解説集」では、屋根や壁の一部の修繕など、遡及適用を受けにくい工事の範囲や、用途変更や大規模修繕、移転の際の緩和規定について具体的に解説されています 。例えば、大谷石自体は不燃材料であるため、防火規定上有利な点も多く、大谷石蔵の意匠を活かした修繕が可能です 。
大谷石活用のためのガイドライン – 安全な保存と活用のために
宇都宮市は、大谷石建造物の適切な保全と活用を促進するため、専門的なガイドラインを発行しています。
- 「大谷石建造物の保全・活用のための耐震診断・補強ガイドライン」: 無筋の大谷石造を対象とした耐震診断法(Is値の算定など)や補強工法の要点がまとめられており、安全性を確保しながら大谷石建築を活用していくための重要な指針となります 。
これらの法規制やガイドラインは複雑であり、個々のケースによって適用が異なります。五月女建設では、これらの法令・ガイドラインを熟知した専門家が、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、必要な手続きをサポートいたします。
大谷石塀に関する注意点
大谷石の塀を設置・改修する際には、建築基準法により高さ1.2メートル以下などの基準が定められていますので注意が必要です 。
無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。
地域と共に生きる大谷石:イベントと文化継承
大谷石は、宇都宮・栃木の地域文化と深く結びついています。その魅力を発信する様々なイベントも開催されており、地域全体で大谷石文化を盛り上げています。
- 大谷グリーン・ツーリズム推進協議会: 宇都宮市大谷町を含む城山地区で、農業体験や里山体験といったイベントを企画・開催。サツマイモ収穫体験や竹を使ったワークショップなど、自然と文化に触れる機会を提供しています 。
- 大谷商工観光協力会: 「大谷夏祭り」をはじめ、大谷資料館の見学ツアー、カネホン採石場でのピザ焼き体験、大谷石を使った雑貨販売など、大谷石を核とした観光振興イベントを多数実施しています 。
- その他地域活動: アートイベントや地域フォーラムなど、様々な形で大谷石文化の発信が行われています 。大谷石蔵マップを参考ください。
これらの活動は、大谷石の魅力を再発見し、地域への愛着を深める素晴らしい機会です。五月女建設も、地域の一員として、こうした活動に注目し、大谷石文化の継承に貢献していきたいと考えています。
まとめ:大切な大谷石建築を、確かな技術で未来へ
この記事では、五月女建設の曳家・改修事例から、大谷石の持つ奥深い魅力、そして大谷石建築に関わる法的な知識や地域の取り組みまで、幅広くご紹介してまいりました。
大谷石建築は、宇都宮・栃木が誇るべき文化遺産です。その価値を理解し、適切な維持管理と必要な改修・移転を行うことで、未来へと美しく引き継いでいくことができます。
五月女建設は、120年以上にわたる歴史で培った確かな技術と豊富な実績、そして大谷石と地域文化への深い理解をもって、皆様の大切な大谷石建築の保存・活用を全力でサポートいたします。
「うちの蔵も相談してみようかな…」 「まずは専門家の意見を聞いてみたい」
そう思われた方は、ぜひ一度、五月女建設にご相談ください。建物の状態診断から、具体的な改修・移転計画のご提案、そして各種申請手続きのサポートまで、トータルでお手伝いさせていただきます。
▼大谷石建築に関するご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。
無料で今すぐ相談!秘密厳守!※お手元に図面を用意すると簡単に入力できます。
[電話番号:0289-62-8235]
私たち五月女建設と一緒に、あなたの大切な大谷石建築の未来を考えてみませんか?
参考資料:
大谷石建造物の保全・活用のための耐震診断・補強ガイドライン(宇都宮市)