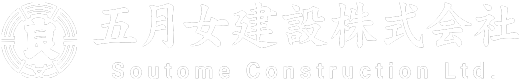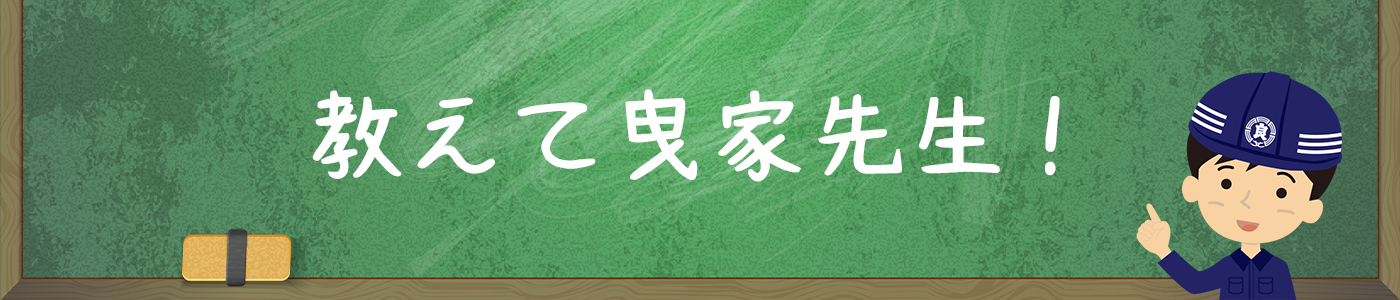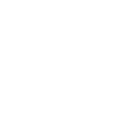大雨・土砂災害に負けない!プロが教える「最強の家」実現ガイド
公開日: 最終更新日:
大雨・土砂災害に負けない!プロが教える「最強の家」実現ガイド【五月女建設】
I. はじめに:その「万が一」は、もう他人事ではない。深刻化する大雨・土砂災害の脅威と、今こそ求められる「住まいの防災力」
近年、日本の気象状況は大きな変化を見せており、「線状降水帯」の発生による局地的な豪雨や、予測困難な「ゲリラ豪雨」が各地で頻発しています 。これにより、これまで安全とされてきた地域でも浸水や土砂災害のリスクが高まり、多くの戸建て住宅所有者が「大雨による浸水への不安」を抱えています 。もはや、「万が一」の事態は他人事ではなく、いつ我が身に降りかかるか分からない現実的な脅威となっています。
このような状況下で、住まいの防災力を高めることは、家族と財産を守るための最重要課題と言えるでしょう。従来の「災害が起きたらどうするか」という受動的な対策から、「災害に負けない家をどう作るか」という能動的な備えへと、意識の転換が求められています。本稿では、深刻化する自然災害の現状を踏まえ、住宅所有者が知っておくべきリスクと対策、そして専門的な技術によって実現可能な「災害に強い家づくり」について、専門家の視点から解説します。この情報が、皆様の安全な住まいづくりの一助となれば幸いです。特に、曳家(ひきや)の技術を基盤に持つ五月女建設のような専門業者による対策は、根本的な安心をもたらす選択肢となり得ます。
自然災害の頻発化は、単に物理的な被害だけでなく、被災された方々には計り知れない精神的な負担をもたらします 。安心して暮らせる住環境を確保することは、日々の生活の質を維持する上でも極めて重要です。そのため、本稿では、災害のメカニズムの理解から、個人でできる対策、そして専門家による恒久的な解決策までを網羅的に提供することを目指します。
II. あなたの家は大丈夫?まず知るべき災害リスク:ハザードマップの徹底活用と潜む危険性
住まいの防災対策を講じる上で、まず把握すべきは、その土地がどのような災害リスクを抱えているかという点です。ここでは、特に大雨時に懸念される浸水被害と土砂災害について、その種類と確認方法を解説します。
浸水 の種類
浸水被害と一口に言っても、その形態は様々です。
- 床上浸水・床下浸水: 建物の床面より上に浸水する「床上浸水」と、床下空間に水が溜まる「床下浸水」があります 。床下浸水であっても、放置すれば建物の耐久性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
- 外水氾濫・内水氾濫: 河川の堤防決壊や越水によって広範囲が浸水する「外水氾濫」と、下水道の排水能力を超えた雨水が市街地にあふれ出す「内水氾濫」があります 。都市部では内水氾濫のリスクも軽視できません。
土砂災害 の種類
山間部や傾斜地では、土砂災害への警戒も不可欠です。主な土砂災害には以下の3つのタイプがあります。

- がけ崩れ: 雨水の浸透や地震などにより、急な斜面が突然崩れ落ちる現象です 。
- 地すべり: 比較的緩やかな斜面が、地下水の影響などで広範囲にわたりゆっくりと滑り動く現象です 。
- 土石流: 大雨などにより、山腹や谷の土砂・石・流木などが水と一体となって高速で流れ下る現象です 。いずれも破壊力が大きく、人命に関わる危険性があります。
ハザードマップ– あなたの地域の「災害カルテ」
これらのリスクを具体的に把握するための第一歩が、各自治体が公表している「ハザードマップ」の確認です。
- 重要性: ハザードマップは、過去の災害履歴や地形データに基づき、災害発生時に浸水が想定される区域や深さ、土砂災害の危険箇所などを示した地図であり、自宅周辺のリスクを客観的に知るための重要なツールです 。
- 入手・確認方法: お住まいの市区町村の窓口やホームページ、または国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」から入手・閲覧が可能です 。土砂災害に関しては、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」や、より危険度の高い「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が色分けで示されています 。
ハザードマップの限界と「見えないリスク」
ハザードマップは非常に有用な情報源ですが、その情報が全てではありません。
- 指定区域外の危険性: 土砂災害警戒区域等に指定されていない区域でも、土砂災害が発生する可能性はゼロではありません 。特に、付近に崖地や小さな沢がある場合は注意が必要です。
- 想定を超える災害: ハザードマップは一定の条件下での予測に基づいて作成されており、想定を超える規模の豪雨や地震が発生した場合には、マップに示された範囲を超えて被害が及ぶこともあり得ます 。
ハザードマップを確認することは防災の基本ですが、それに加えて、自宅周辺の地形や過去の災害の有無、近年の気象状況の変化などを総合的に考慮し、潜在的なリスクについても意識を向けることが重要です。例えば、以前は問題なかった場所でも、周辺の開発や環境の変化によって水はけが悪くなったり、斜面の安定性が低下したりするケースも考えられます。このような「見えないリスク」を認識し、より能動的に情報を収集し、専門家による現地調査を検討することも、真の安全を確保するためには有効な手段となり得ます。
相談だけでも大歓迎です。あなたの家の災害リスクを無料で調査いたします。
プロに調査を頼んでみる
III. まずは自分でできること!今日から始めるDIY「我が家の防災レベルアップ」術
災害リスクを把握した上で、次に着手すべきは、個人でできる範囲での防災対策です。ここでは、大雨・浸水と土砂災害それぞれに対する具体的な備えと、共通して準備しておきたい項目について解説します。
A. 大雨・浸水への備え
情報収集と避難計画
- 気象情報の確認: テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて、最新の気象情報や警報・注意報をこまめに確認しましょう 。特に、自治体から発令される「警戒レベル」の意味を理解し、適切な行動をとることが重要です 。
- 家族会議: 万が一の場合に備え、家族で避難場所や避難経路、連絡方法などを事前に話し合っておくことが大切です 。
家屋への浸水対策(初期段階)
- 貴重品等の移動: 浸水の恐れがある場合は、家財道具や家電製品、食料品など、濡れて困るものはできるだけ高い場所(2階など)へ移動させます 。低い位置にあるコンセントは、プラグを抜いておきましょう 。
- 土のう・水のうの設置: 玄関や勝手口など、水の浸入経路となり得る箇所には、土のうや水のうを設置して浸水を防ぎます。土のう袋はホームセンターなどで入手可能で、水で膨らむ吸水性土のうも便利です 。ただし、これらの対策はあくまで初期の浅い浸水に対する応急処置であり、水位が高くなると効果は限定的です 。
- 排水溝からの逆流防止: 大雨時には下水道から汚水が逆流することがあります。トイレや風呂場、洗濯機の排水溝などに、水を入れたゴミ袋(水のう)を置くことで、逆流をある程度抑えることができます 。
浸水後の衛生対策
- 万が一浸水してしまった場合は、水が引いた後の清掃と消毒が不可欠です。汚泥や汚水には細菌が含まれている可能性があり、感染症のリスクがあるため、ゴム手袋やマスクを着用し、適切な消毒薬(次亜塩素酸ナトリウムなど)を使用して家屋内外を消毒しましょう 。
B. 土砂災害への備え
危険のサインを見逃さない!土砂災害の前兆現象
土砂災害は発生すると一瞬で被害が拡大するため、前兆現象に気づき、早期に避難することが生死を分けます。
- がけ崩れ: 斜面にひび割れができる、小石がパラパラ落ちてくる、斜面から水が湧き出す、地鳴りがする 。
- 地すべり: 地面にひび割れや段差ができる、井戸や沢の水が濁る、樹木が傾く 。
- 土石流: 山鳴りがする、川の水が急に濁って流木が混じる、腐った土の臭いがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる 。
早期避難の重要性
- 上記のような前兆現象に気づいたり、身の危険を感じたりした場合は、避難指示が出ていなくても自主的に避難を開始することが重要です 。
- 避難場所への移動が困難な場合は、自宅の2階以上の崖から離れた部屋や、近隣の頑丈な建物の上階へ避難する「垂直避難」も有効な場合があります 。
避難時の服装と注意点
- 避難する際は、ヘルメットや防災頭巾で頭部を保護し、長袖・長ズボン、底の厚い運動靴など、動きやすく安全な服装を心がけましょう。両手が使えるように荷物はリュックサックに入れるのが基本です 。
C. 共通の備え
非常用持ち出し袋の準備
- 飲料水、食料品(最低3日分)、携帯ラジオ、懐中電灯、応急医薬品、貴重品(現金、預金通帳、保険証など)、モバイルバッテリー、常備薬などをリュックにまとめておき、すぐに持ち出せるように準備しておきましょう 。
家屋周りの点検・清掃
- 日頃から、雨どいや側溝、排水溝などが落ち葉やゴミで詰まっていないか点検し、清掃しておくことが浸水リスクの軽減につながります 。
これらの個人でできる対策は、被害を最小限に抑えるために非常に重要です。しかし、大規模な災害や、根本的な土地の脆弱性に起因する問題に対しては、これらの対策だけでは限界があることも認識しておく必要があります。
IV. DIY対策の限界と、プロによる「根本解決」の必要性
前章で述べた個人でできる防災対策は、初期対応や被害軽減に有効ですが、深刻な災害や繰り返される脅威に対しては、その効果には限界があります。特に、床下浸水や地盤沈下といった問題は、住まいに深刻かつ長期的なダメージを与え、根本的な解決には専門家の力が必要となります。
一時しのぎの対策では防ぎきれない現実
土のうの設置や家財の移動といったDIY対策は、あくまで一時的な対応です。
- 繰り返す浸水: 頻繁に小規模な浸水に見舞われる地域では、その都度の清掃や乾燥、精神的な負担は計り知れません。DIY対策では、この根本的な脆弱性を解消することはできません。
- 大規模災害: 想定を超える豪雨による深い浸水や、勢いの強い水の流れに対しては、簡易的な防水措置はすぐに無力化してしまいます 。
- 土砂災害リスク: 土砂災害の危険性が高い立地では、観察や簡易的な土留め程度では、大規模な崩壊を防ぐことは困難です。
床下浸水・地盤沈下が家に与える深刻なダメージ
床下浸水の影響
床下浸水は、目に見えにくい場所で深刻な問題を引き起こします。
- 汚染と腐食: 床下に流れ込むのは単なる雨水ではなく、泥や下水、様々な汚染物質を含む可能性があります 。これらが木材の腐食や金属部分の錆を進行させ、建物の耐久性を著しく低下させます。
- カビ・害虫の発生: 床下の湿気はカビやシロアリなどの害虫にとって格好の繁殖環境となり、健康被害やさらなる構造材の劣化を招きます 。
- 清掃・乾燥の困難さ: 床下の汚泥除去、清掃、完全な乾燥は個人で行うには非常に困難です。不十分な乾燥は問題を長期化させ、数週間から数ヶ月を要することもあります 。専門業者による適切な処置が不可欠となるケースが少なくありません。
- 電気系統への影響: 床下の配線が浸水すると、漏電や火災のリスクも生じます 。

家の傾き・地盤沈下の影響
大雨や地震による液状化、あるいは元々の地盤の弱さから地盤沈下が発生すると、家が傾くことがあります。
- 主な原因: 地盤沈下、地震による液状化、盛土・埋立地の圧密沈下、近隣の工事の影響、さらにはシロアリによる土台の食害や建物の老朽化も原因となり得ます 。特に、集中豪雨による土壌の水分量増加は、地盤の緩みや液状化を誘発し、沈下のリスクを高めます。
- 放置するリスク:
- 構造的な問題: 建物の傾きは、構造体に不均等な負荷をかけ続け、柱や梁の歪み、基礎のひび割れなどを引き起こし、最悪の場合は倒壊に至る危険性があります 。
-
- 建具の不具合: ドアや窓の開閉が困難になったり、隙間風が生じたりします 。
-
- 雨漏り・設備の不具合: 外壁の亀裂から雨水が浸入しやすくなったり、配管に無理な力がかかり水漏れの原因になったりします 。
- 資産価値の低下:傾いた家は、当然ながら不動産としての資産価値が大幅に低下します 。
- 健康被害: 傾いた家での生活は、平衡感覚の異常や自律神経の乱れを引き起こし、めまい、頭痛、吐き気、肩こり、不眠、食欲不振といった様々な健康被害を招くことが報告されています 。これらの症状は原因不明の体調不良として長年悩まされることもあり、生活の質を著しく損ないます。
家の傾きが引き起こす健康被害と生活への影響
| 傾斜角度の目安 (度 / 分数) | 健康への影響の例 | 生活への影響の例 |
|---|---|---|
| 約0.29° (5/1000) | 傾斜を感じ始める | 不同沈下を意識し始める |
| 約0.34° (6/1000) | 不同沈下を意識する | ビー玉が転がる、物が滑りやすい |
| 約0.46° (8/1000) | 傾斜に対して強い意識、苦情の多発 | ドアや窓の開閉に違和感が出始める |
| 約0.6° (10/1000) | めまいや頭痛が生じ、水平復元工事を検討するレベル。平衡感覚の乱れ、肩こり。 | ドアや窓の開閉がしづらくなる、隙間風。 |
| 1°~3° (約1/60~1/20) | 頭重感、浮動感、めまい、頭痛、吐き気、食欲不振など比較的重い症状。自律神経の乱れによる不眠も。 | 壁紙のシワや亀裂、外壁のひび割れ、雨漏りのリスク増大。 |
| 4°以上 (約1/15以上) | 強い牽引感、疲労感、睡眠障害が顕著に。正常な環境でものが傾いて見えることがある。 | 構造的な歪みが進行し、建物の安全性が著しく低下。配管や電気設備への不具合リスクも高まる。資産価値の著しい低下。 |
出典: 建物の傾きによる健康障害 – 日本建築学会 を基に各種情報を加えて作成。症状の出方には個人差があります。
繰り返される浸水被害や、一度発生してしまった地盤沈下・家の傾きは、表面的な修繕だけでは解決しません。それは病気の「対症療法」のようなもので、根本的な原因が残っている限り、問題は再発し続けます。真の安心と安全を取り戻すためには、問題の根源にアプローチする「根本治療」、すなわち専門家による確かな技術に基づいた対策が不可欠となるのです。
V.災害に強い家づくり:曳家技術を活かした「嵩上げ工事」と「沈下修正工事」で実現
DIY対策の限界が見えてきたとき、次に考えるべきは専門家による根本的な解決策です。五月女建設は、建物をそのまま移動させる高度な「曳家(ひきや)」の技術を核とし、その専門性を活かした「嵩上げ工事」と「沈下修正工事」で、災害に強い家づくりをサポートします。
曳家(ひきや)の五月女建設だからできること
曳家とは、建物を解体せずにそのままの状態で持ち上げ、移動、回転させる特殊な工法です 。この作業には、建物の構造に対する深い理解、精密な重量計算、そしてミリ単位の精度でのジャッキアップ技術が不可欠です。五月女建設が長年培ってきたこの曳家技術こそが、高品質な嵩上げ工事や沈下修正工事を可能にする基盤となっています。一般的な建設業者では対応が難しい複雑な状況でも、曳家の専門知識と経験を活かして最適な解決策を提案できるのが強みです。
A. 浸水被害を根本から防ぐ「嵩上げ工事」
嵩上げ工事とは?
嵩上げ工事とは、既存の建物を基礎ごと、あるいは建物本体をジャッキアップし、地盤面からの高さを上げることで、浸水被害を根本的に防ぐ工事です 。ハザードマップで示される想定浸水深や、近年の豪雨被害の状況を考慮し、安全な高さまで建物を持ち上げます。
メリット
- 直接的な浸水被害の防止: 床上浸水のリスクを大幅に低減し、大切な家財や生活空間を守ります 。
- 計画的な高さ設定: 想定される水位に合わせて、建物を持ち上げる高さを自由に設定できます 。
- コスト効率: 建物を移動させずにその場で嵩上げする場合、既存の上下水道管や電線などを再利用できることが多く、比較的低コストでの工事が可能です 。
- 床下環境の改善: 床下の通気性が向上し、湿気によるカビや腐朽、害虫の発生を抑制する効果も期待できます(洗濯機のかさ上げによる通気性向上の効果と同様の原理 )。
デメリットと対策
- アクセス性の変化: 玄関や勝手口までの階段の段数が増えるため、生活動線に影響が出ることがあります 。スロープの設置や、バリアフリーに配慮した設計、庭の高さを上げることで対応可能です。
- 外観の変化: 建物の高さが変わるため外観の印象も変化しますが、適切な設計と外構計画により調和の取れた仕上がりにできます。
工事の流れ(イメージ)
曳家技術を応用し、建物を安全かつ精密にジャッキアップ。新たな高さに合わせて基礎を再構築、または補強し、建物を慎重に下ろして固定します。全工程において、建物の歪みや損傷を防ぐための細心の注意が払われます。
費用相場と工期
費用は建物の規模、構造、嵩上げする高さ、基礎の状態などにより大きく変動します。一般的な木造住宅の場合、基礎工事を含めて数百万円規模になることがありますが 、既存設備を再利用できる場合はコストを抑えられることもあります 。工期も状況によりますが、数週間から数ヶ月が目安です。
助成金制度の活用
自治体によっては、住宅の浸水対策としての嵩上げ工事に対して助成金制度を設けている場合があります 。例えば、新潟市では床上浸水被害があった区域の住宅嵩上げ工事に対し、工事費用の1/2(上限100万円)を助成する制度があります 。お住まいの自治体に確認してみることをお勧めします。
施工事例の紹介
五月女建設では、これまでに多くの嵩上げ工事を手掛けてきました。実際の施工例(写真やブログ などで紹介されるような事例)を通じて、工事の品質や効果を確認できます。
B. 家の傾きを直し、安全と資産価値を回復する「沈下修正工事」
沈下修正工事とは?
地盤沈下や液状化などにより傾いてしまった建物を、元の水平な状態に修正する工事です 。放置すれば建物の寿命を縮めるだけでなく、住む人の健康にも悪影響を及ぼすため、早期の対応が重要です。
なぜ沈下修正が必要か
第IV章で詳述した通り、家の傾きは構造的な問題、建具の不具合、雨漏り、資産価値の低下、そして深刻な健康被害を引き起こします。これらのリスクを解消し、安全で快適な住環境を取り戻すために沈下修正工事は不可欠です。
五月女建設が採用する主な工法と特徴
沈下修正工事には様々な工法があり、建物の構造、傾きの原因、地盤の状態、予算などに応じて最適なものが選択されます 。五月女建設では、曳家で培った精密なジャッキアップ技術と構造知識を活かし、以下のような工法に対応しています。
主な沈下修正工法比較(五月女建設対応例)
| 工法名 | 概要 | メリット | デメリット・注意点 | 費用目安(一般的な木造住宅) | 工期目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土台揚げ工法 | 基礎と土台を切り離し、ジャッキで木造部分を持ち上げて水平にする 。 | 比較的安価で工期が短い。部分的な沈下にも対応しやすい。 | 地盤自体の補強は行わないため、地盤沈下が進行中の場合は再沈下の可能性あり。基礎の補修が必要な場合がある。 | 150万円~400万円 | 約1~2週間 |
| 耐圧版工法 | 基礎下を掘削し、耐圧版を設置。その上にジャッキをセットして建物を持ち上げる 。 | 比較的広範囲の沈下に対応可能。 | 地盤が軟弱な場合は再沈下の可能性。残土処理が発生。 | 200万円~800万円 | 約3~5週間 |
| 薬液注入工法 | 基礎下の地盤にセメント系などの薬液を注入し、地盤を固めて強化すると同時に、注入圧で建物を持ち上げる 。 | 地盤改良効果も期待できる。比較的狭いスペースでも施工可能。 | 地盤状況により効果に差。近隣構造物への影響に注意。布基礎では施工不可の場合も。 | 250万円~800万円 | 約1~3週間 |
| 鋼管杭圧入工法 | 基礎下に鋼管杭を強固な支持層まで圧入し、その杭を反力として建物をジャッキアップする 。 | 再沈下の可能性が極めて低い。軟弱地盤や重量のある建物にも有効。 | 費用が比較的高額になる傾向。残土処理が発生。 | 400万円~1500万円 | 約4~8週間 |
五月女建設施工事例などの情報を基に作成。費用や工期はあくまで目安であり、個々の状況により異なります。
五月女建設では、詳細な地盤調査と建物診断に基づき、これらの工法の中から最も効果的かつ経済的なプランを提案します。複数の選択肢を持つことで、画一的な対応ではなく、個々の住宅の状況に最適化されたオーダーメイドの修復が可能になります。これは、顧客にとって最良の結果を追求する姿勢の表れです。
工事の流れ(イメージ)
傾きの原因調査、地盤調査、施工計画の策定後、選択された工法に基づき、精密なジャッキコントロールで建物をミリ単位で修正していきます。
費用相場と工期
上記の表に示した通り、工法や建物の状況によって費用と工期は大きく異なります。一般的に、家の傾き修正工事の相場は約300万円程度とされますが、部分的な修正であれば100万円台から、複雑なケースでは数百万円以上になることもあります 。
施工事例とお客様の声
嵩上げ工事 栃木県宇都宮市|施工事例|木造二階建住宅 防腐剤塗布
沈下修正 栃木県鹿沼市|施工事例|大雨災害 床上浸水 基礎の洗掘
沈下修正工事 栃木県鹿沼市|施工事例|地盤沈下 アンダーピニング工法 木造二階建住宅
「ビー玉が転がらなくなった」「原因不明の体調不良が改善した」「安心して眠れるようになった」など、沈下修正工事によって生活の質が向上したという声が多く寄せられています 。これらの実例は、工事の確かな効果を物語っています。
五月女建設の「嵩上げ工事」と「沈下修正工事」は、単に建物を物理的に修復するだけでなく、そこに住む人々の安全と安心、そして大切な資産価値を守るための投資です。曳家の専門技術があるからこそ提供できる、根本的な解決策と言えるでしょう。
VI. なぜ五月女建設が選ばれるのか?「曳家のプロ」だからこその安心と信頼
大切な住まいの大規模な工事を任せるにあたり、業者選びは最も重要なポイントの一つです。五月女建設が、嵩上げ工事や沈下修正工事といった専門性の高い分野で選ばれ続ける理由には、曳家(ひきや)のプロフェッショナルとしての確かな技術力と、顧客に寄り添う真摯な姿勢があります。

専門知識と豊富な実績
- 曳家技術という核心的強み: 五月女建設の最大の強みは、前述の通り、建物を安全かつ精密に動かす「曳家」の高度な専門技術です 。この技術は、家を持ち上げる嵩上げ工事や、傾いた家をミリ単位で修正する沈下修正工事において、他社にはない精度と安全性をもたらします。構造力学や地盤に関する深い知識がなければ、これらの工事を成功させることはできません。
- 長年の経験と実績: 数多くの嵩上げ工事や沈下修正工事を手掛けてきた実績は、信頼の証です。様々な現場状況に対応してきた経験が、個々の住宅に最適な工法を選定し、質の高い工事を提供する力となっています 。
- 有資格者による施工: 建設業許可はもちろんのこと、土木施工管理技士や建築士といった国家資格を持つ専門スタッフが在籍していることは、技術力の高さを客観的に示すものです 。これらの資格は、工事の品質、安全性、法令遵守に対する意識の高さを裏付けています。
一貫した責任施工と品質管理
- 直接施工へのこだわり: 大規模な工事では、下請け業者に作業を委託するケースも少なくありません。しかし、五月女建設では可能な限り直接施工にこだわり、工事の全工程に責任を持つ体制を重視しています。これにより、品質管理の徹底と、万が一の際の迅速な対応が可能となります 。
- 徹底した事前調査と最適な提案: 家の傾きや沈下の原因は一軒一軒異なります。五月女建設では、着工前に詳細な現地調査(地盤調査、建物診断など)を行い、その結果に基づいて各住宅に最適な工法と施工計画を提案します 。画一的な対応ではなく、オーダーメイドの解決策を提供することが、顧客満足につながると考えています。
- 安全管理の徹底: 工事中の安全は何よりも優先されるべき事項です。五月女建設では、作業員の安全はもちろん、近隣住民の方々への配慮も怠らず、徹底した安全管理のもとで工事を進めます 。
お客様との丁寧なコミュニケーション
- わかりやすい説明: 専門的な工事内容であっても、顧客が十分に理解し納得できるよう、専門用語を避け、平易な言葉で丁寧に説明することを心がけています 。不安や疑問点があれば、何度でも誠実に対応します。
- 透明性の高い見積もりと契約: 見積もり内容を詳細に提示し、追加費用の可能性についても事前に説明します。契約を急がせるようなことは決してありません 。無料相談や現地調査、見積もりサービスを提供し、顧客が安心して検討できる環境を整えています 。
万全のアフターサポートと保証
- 工事後の安心: 工事が完了した後も、長期的な安心を提供するためのアフターサポートや保証制度を設けています 。工事内容に応じた保証は、施工品質に対する自信の表れでもあります 。
家の傾き修正や嵩上げ工事は、決して安価な投資ではありません。だからこそ、技術力はもちろんのこと、顧客の不安に寄り添い、真摯に対応してくれる信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも重要です。五月女建設は、曳家のプロとしての誇りを持ち、一軒一軒の住まいと真剣に向き合い、最高の技術とサービスを提供することをお約束します。
VII. まとめ:未来の安心は、今日の決断から。災害に屈しない住まいを。
本稿を通じて、近年ますます深刻化する大雨や土砂災害のリスク、そしてそれらに対する備えの重要性について解説してきました。ハザードマップによるリスク確認や、個人でできる応急的な対策は確かに有効ですが、根本的な解決や大規模な災害に対しては限界があることも明らかになりました。特に、床下浸水がもたらす長期的なダメージや、家の傾きが引き起こす構造的・健康的な問題は、放置すれば取り返しのつかない事態を招きかねません。
このような深刻な問題に対し、五月女建設が提供する「嵩上げ工事」と「沈下修正工事」は、曳家(ひきや)の専門技術を駆使した、まさに「根本治療」と言える解決策です。浸水リスクのある地域では家全体を安全な高さまで持ち上げ、地盤沈下や液状化で傾いてしまった家はミリ単位で水平に修正する。これらの工事は、単に建物を修復するだけでなく、そこに住む家族の安全と安心な未来を守り、大切な資産価値を維持することにつながります。
「我が家は本当に次の『想定外』の災害に耐えられるだろうか?」 「いつか来るかもしれない、と不安を抱えながら暮らすのはもう終わりにしたい。」
もし、少しでもこのようなお考えをお持ちでしたら、どうか手遅れになる前にまず相談してください。
私達五月女建設では、お客様一人ひとりの状況やお悩みに真摯に耳を傾け、専門家の視点から最適なアドバイスと解決策をご提案いたします。まずは、お気軽にご相談ください。専門スタッフによる現地調査やお見積もりは無料で承っております(状況により有料となる場合もございますので、事前にお問い合わせください)。
お問い合わせ先: 五月女建設株式会社
- お電話でのお問い合わせ: [0289-62-8235]
- ウェブ相談(携帯電話でご相談できます)
- 無料相談・現地調査のお申し込み: 上記電話番号またはウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
災害に屈しない、本当に強い家を。五月女建設が、その実現を全力でサポートいたします。