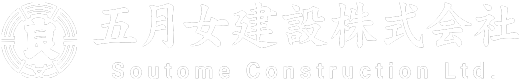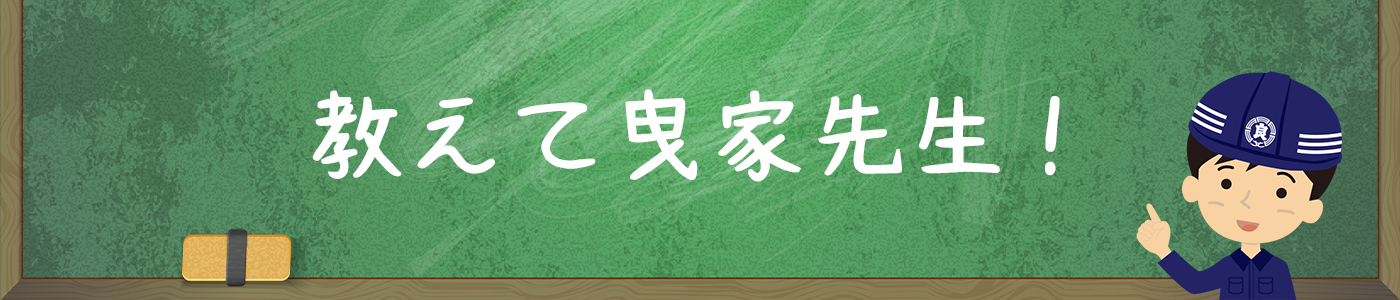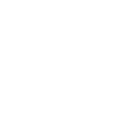【曳家】法律トラブルを回避!建築基準法・民法・都市計画法・土地区画整理法をわかりやすく解説
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! 第五話 ~絶対に損しない法律のコツ~ 後悔しないための法律のポイント徹底解説!
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
こんにちは曳家先生です。第四回目の前回は、「絶対に損しない失敗回避のコツ」についてお話ししました。第五回目の今回は「曳家にまつわる法律」について学んでいきましょう。法律は、私たちの生活のあらゆる場面で関わっています。契約を結ぶとき、交通事故に遭ったとき、相続をするとき、法律を知らなければ、不利益を被る可能性があります。そこで今回は、曳家工事に必要な「絶対に損しない法律のコツ」についてお話しします。
曳家は違法?法律で認められている行為なのか
結論から言うと、曳家自体は法律で禁止されている行為ではありません。 しかし、曳家の実施にあたっては、建築基準法、道路法、民法など、様々な法律や規制を遵守する必要があります。これらの法律や規制に違反すると、工事の中止命令や罰則を受ける可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
法律トラブルから家を守る!|曳家工事で失敗しないための法律知識
「曳家工事って一体どんな法律が関係するの?」 「専門用語ばかりで、契約書の内容がよくわからない…」
そんな不安を抱えているあなたへ。この記事では、曳家工事に関わる法律の基本から、絶対に損をしないための具体的な対策まで、わかりやすく解説します!
なぜ曳家するにも法律知識が必要なの?
なぜ法律について知らなければならないのでしょう?
その答えは「曳家工事も建築基準法に定められた建築行為」であり、何より、「曳家工事は、あなたの大切な家を動かす人生の一大プロジェクト」だからです。
だからこそ、
- 安心して工事を進めるため
- 後々のトラブルを避けるため
- あなたの権利を守るため
に、法律知識は欠かせません。
曳家工事に関連の深い4種類の法律を具体的に解説!
さてそれでは、曳家工事にはどんな法律が関連するのでしょうか
各種法律について学んでいきましょう。
曳家に関連する法律は大きく分けると次の4つ。

1.建築基準法
建物に関する基準を定めて、国民の健康及び財産の保護と、公共の福祉の増進を目的とする。
関連記事:
「曳家での建築確認のコツ!建築基準法・既存不適格など曳家先生が解説!」
・・・つまり、命(健康)と財産(建物)を守るルール
2.民法
日常的な取引、金融取引、その他各種契約や財産等を規律することを目的とする。
・・・つまり、契約やお金に関するルール
3.都市計画法・土地区画整理法
都市の健全な発展と秩序ある整備、健全な市街地の造成を図る。共に公共の福祉の増進に資することを目的とする。
土地区画整理法|e-Gov法令検索
・・・つまり、街づくりのルール
4.その他の法律
その他道路法・河川法・文化財保護法など
例えば、建築基準法では、曳家工事を行う際には、建築基準に適合していることを確認する必要があります。また、都市計画法では、曳家工事を行う際には、都市計画に適合していることを確認する必要があります。加えて民法に則った形での契約と請求権の行使が必要になります。
これらを無視すると、
- 工事が中断してしまう
- 余計なお金がかかる
- 近隣トラブルに発展する
なんてことも…

そこで今回は、絶対に損しない法律のコツをご紹介します。
曳家に必要な許可・申請手続き
実際に曳家を行うには、関係各所への許可申請が不可欠です。無許可で工事を行うと、工事の中止命令や罰則の対象となる可能性があります。ここでは、曳家を行う上で一般的に必要となる許可・申請手続きについて解説します。
建築確認申請が必要となるケース
曳家において、建築確認申請が必要となるのは、建物の「構造」「位置」「規模」に重要な変更が生じる場合です。具体的には以下のようなケースが該当します。
-
建物の基礎を新設する場合: 曳家によって基礎の位置が大きく変わる場合や、基礎を造り直す場合は、新たに建築確認申請が必要となります。
-
建物の構造に変更を加える場合: 耐震補強などのために、建物の主要構造部(柱、梁、壁、床、屋根)に変更を加える場合は、建築確認申請が必要となります。
-
建物の用途を変更する場合: 例えば、住宅を店舗に変更するなど、建物の用途を変更する場合は、建築確認申請が必要となります。
建築確認申請は、工事に着手する前に行う必要があり、審査には一定の期間を要します。事前に計画を立て、余裕をもって申請を行いましょう。
関連記事:
曳家での建築確認のコツ!建築基準法・既存不適格など曳家先生が解説!
その他の許可・申請が必要となる場合
上記以外にも、曳家の内容や場所によっては、以下のような許可・申請が必要となる場合があります。
-
文化財保護法に基づく許可: 曳家を行う建物が文化財に指定されている場合や、埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合は、文化庁長官または都道府県・市町村教育委員会の許可が必要となります。
-
景観法に基づく届出: 景観計画区域内で一定規模以上の建築物の外観を変更する場合は、事前に地方公共団体への届出が必要となる場合があります。
-
自治体の条例に基づく許可・届出: 各自治体で独自の条例を定めている場合があります。例えば、騒音や振動に関する規制、建設リサイクル法に基づく届出などが該当します。
事前に専門家や関係機関に相談し、必要な手続きを漏れなく行うようにしましょう。
曳家が及ぼす権利関係への影響
曳家は物理的に建物を移動させる行為であるため、関連する権利関係にも影響を与える可能性があります。ここでは、曳家が及ぼす可能性のある主な権利関係への影響と注意点について解説します。
所有権・抵当権への影響と手続き
建物の所有権は、曳家によって移動しても基本的には変わりません。しかし、建物の所在地が変更となる場合は、不動産登記簿の変更登記が必要となります。
また、建物に抵当権が設定されている場合、曳家によって抵当権の効力が及ばなくなる可能性があります。そのため、事前に抵当権者の同意を得て、抵当権の目的の変更登記や追加設定登記を行う必要があります。これらの手続きを怠ると、後々法的トラブルに発展する可能性がありますので、必ず専門家と相談の上、適切な手続きを行いましょう。
借地権付き建物の曳家における注意点
借地権付きの建物を曳家する場合、地主の承諾が不可欠です。借地契約の内容によっては、建物の改築や移転が制限されている場合があります。無断で曳家を行うと、契約違反となり、借地契約の解除や損害賠償請求を受ける可能性があります。
曳家を検討する際は、まず借地契約の内容を確認し、地主に曳家の計画を説明し、書面による承諾を得るようにしましょう。また、曳家後に借地契約を更新する必要がある場合も、地主との協議が必要となります。
近隣住民とのトラブルを避けるために
曳家工事は、騒音や振動、工事車両の通行などにより、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。事前の説明不足や配慮の欠如は、近隣住民とのトラブルの原因となります。
トラブルを未然に防ぐためには、事前に近隣住民に対して曳家の目的、工事期間、騒音対策などを丁寧に説明し、理解と協力を求めることが重要です。場合によっては、工事による影響に対する補償や、曳家後の建物の位置関係に関する合意形成が必要となることもあります。
家に関する法律トラブル事例と対策
残念ながら、曳家工事を巡っては、様々な法律トラブルが発生する可能性があります。ここでは、実際に起こりうるトラブル事例とその対策について解説します。
曳家工事における契約上の注意点
曳家工事は高額な費用がかかるため、業者との契約は慎重に行う必要があります。契約書には、工事内容、工期、費用、支払い条件、瑕疵担保責任、保証内容などを明確に記載してもらいましょう。特に、追加費用が発生する条件や、万が一の事態における責任の所在については、曖昧なままにせず、しっかりと確認しておくことが重要です。
契約締結前に、複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することも大切です。また、契約内容について不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
曳家中の事故・損害に関する責任
曳家工事中には、建物の損傷や、第三者への損害が発生するリスクがあります。これらの事故や損害に関する責任は、基本的に工事を請け負った業者にありますが、契約内容や事故の状況によっては、施主にも責任が及ぶ場合があります。
万が一の事態に備え、業者には適切な賠償責任保険への加入を義務付けるとともに、施主自身も火災保険や請負業者賠償責任保険への加入を検討することが重要です。また、工事開始前に、損害が発生した場合の責任範囲や賠償に関する取り決めを業者と明確にしておくことも大切です。
曳家に関する法律トラブル事例と対策
残念ながら、曳家工事を巡っては、様々な法律トラブルが発生する可能性があります。ここでは、実際に起こりうるトラブル事例とその対策について解説します。
曳家工事における契約上の注意点
曳家工事は高額な費用がかかるため、業者との契約は慎重に行う必要があります。契約書には、工事内容、工期、費用、支払い条件、瑕疵担保責任、保証内容などを明確に記載してもらいましょう。特に、追加費用が発生する条件や、万が一の事態における責任の所在については、曖昧なままにせず、しっかりと確認しておくことが重要です。
契約締結前に、複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することも大切です。また、契約内容について不明な点があれば、担当者に説明を求め、必要があれば弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
曳家中の事故・損害に関する責任
曳家工事中には、建物の損傷や、第三者への損害が発生するリスクがあります。これらの事故や損害に関する責任は、基本的に工事を請け負った業者にありますが、契約内容や事故の状況によっては、施主にも責任が及ぶ場合があります。
万が一の事態に備え、業者には適切な賠償責任保険への加入を義務付けるとともに、施主自身も火災保険や請負業者賠償責任保険への加入を検討することが重要です。また、工事開始前に、損害が発生した場合の責任範囲や賠償に関する取り決めを業者と明確にしておくことも大切です。
民法改正による契約不適合責任の解説
1.概要と改正の背景
2020年4月1日の民法改正(債権法改正)により、従来の「瑕疵担保責任」が廃止され、「契約不適合責任」に置き換えられました。これは、売買契約や請負契約で引き渡された目的物(目的工事物)が、契約で定めた「種類・品質・数量」に適合していない場合に、請負業者が発注者に対して負う責任です。
改正前の瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」(通常の注意では発見できない欠陥)が対象で、買主が損害賠償または契約解除を請求できるにとどまっていました。しかし、改正後は「契約内容に適合しない」場合すべてが対象となり、より広範な保護が買主に与えられています。
2. 契約不適合責任の内容
対象となる不適合の範囲
-
種類不適合:契約と異なる種類の商品が納品された場合
-
品質不適合:契約で定めた品質を満たしていない場合
-
数量不適合:契約数量に満たない場合
買主が行使できる4つの権利
| 請求権 | 内容 |
|---|---|
| 追完請求権 | 修理、代替品の引渡し、不足分の引渡しなど、契約内容に適合するように求める権利 |
| 損害賠償請求権 | 契約不適合による損害の補填を請求できる(信頼利益・履行利益も含む) |
| 代金減額請求権 | 不適合の程度に応じて、購入代金の減額を請求できる(追完がなされない場合など) |
| 解除権 | 追完がなされない場合や重大な不適合がある場合、契約を解除し代金返還を請求できる |
請求権行使の流れ
3. 瑕疵担保責任との主な違い
| 項目 | 瑕疵担保責任(旧法) | 契約不適合責任(改正法) |
|---|---|---|
| 対象 | 隠れた瑕疵 | 種類・品質・数量の不適合すべて |
| 買主の権利 | 損害賠償請求、契約解除 | 追完請求、損害賠償請求、代金減額請求、解除権 |
| 立証責任 | 「隠れた」ことの立証が必要 | 不適合の存在のみでよい |
| 適用範囲 | 特定物かどうかで制限あり | 特定物・不特定物を問わず適用 |
| 買主の善意無過失 | 必要(知らなかったこと・過失がないこと) | 不要 |
4. 責任追及の期間制限
-
主は、契約不適合を知った時から原則1年以内に売主へ通知しなければなりません。
-
商人間の取引(会社間など)では、目的物を受け取った後、遅滞なく検査し、発見次第すぐに通知する必要があります。

5. 免責や注意点
-
買主の責めに帰すべき事由(たとえば、買主の指示ミスなど)による不適合は、売主の責任とはなりません。
-
契約書で責任範囲や期間を個別に定めることも可能ですが、消費者契約などでは制限がある場合もあります。
6. まとめ
民法改正により、「契約不適合責任」は、取引の安全性や買主保護を強化する内容となっています。発注者・請負業者ともに、契約内容の明確化と、納品物の確認・通知義務に十分注意する必要があります。
曳家業者を選ぶ際の法的注意点
信頼できる曳家業者を選ぶことは、曳家の成功に不可欠です。ここでは、業者を選ぶ際に特に注意すべき法的側面について解説します。
建設業許可・作業に関する資格の確認
曳家工事は専門的な技術を要する建設工事にあたるため、一定規模以上の工事を請け負うには、建設業法に基づく建設業許可が必要となります。許可を受けている業者は、一定の技術力や経営能力があると認められているため、信頼性の判断材料の一つとなります。
業者を選ぶ際には、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けているか、許可の種類(建築工事業など)を確認しましょう。建設業許可証の提示を求めるか、国土交通省の建設業者・宅建業者検索システムなどで確認することができます。
業者の実績と保険加入状況の確認
建設業許可の有無だけでなく、業者の曳家工事の実績や、賠償責任保険への加入状況も確認しましょう。豊富な実績を持つ業者は、様々な状況に対応できるノウハウを持っていると考えられます。
また、万が一の事故や損害に備え、業者が適切な賠償責任保険に加入しているかを確認することは非常に重要です。保険証券の提示を求めるなどして、加入状況をしっかりと確認しましょう。
明日からすぐにできる!|失敗しないための5つのポイント
- 1.専門家に相談する
法律に関係するトラブルに巻き込まれたら、まずは専門家に相談することが重要です。民法であれば弁護士、建築基準法であれば建築士など、法律の専門家は、法律の知識を豊富に持っており、あなたの状況にあったアドバイスをすることができます。また業者を選ぶ際にも法律に詳しい担当者かどうかを見極める必要があります。法律に詳しい業者を選ぶことで、知らないことで起きるトラブルを未然に防ぐことができます。
関連記事
【曳家の業者選び】評判・口コミで選ぶ優良会社|選び方のコツも解説【チェックシート付き】
- 2.契約書はよく読む
契約書は、法律の専門家が作成したものです。そのため、契約書には、法律に詳しくない一般の人には理解しにくい内容が含まれていることもあります。しかし、契約書を結ぶ前に、必ず契約書をよく読み、説明を聞いて内容を理解した上で、署名捺印をしましょう。例えば、曳家工事において起きることがあるひび割れや歪みを始めとした建物の欠陥には2020年に民法改正での契約不適合責任等の法律が争点となることがあります。わからないことはどんどん質問しましょう。さらに詳しくはこちらのサイトを参照して下さい。
契約書の読み方の基本とコツ
- 3.証拠を残しておく
法律に関係するトラブルに巻き込まれると、証拠が重要となります。トラブルが発生する前に、できるだけ証拠を残しておきましょう。証拠には、書類、写真、動画など、何でもかまいません。事実の検証を当事者だけでなく第三者が行うことで、より公平な解決策を導くことができます。
- 4.早めに行動する
法律に関係するトラブルが発生したら、早めに行動しましょう。早めに行動することで、状況を改善する可能性が高くなります。またトラブルを未然に防ぐために不安を感じたらすぐに担当者に相談しましょう。不安を解消することが安心安全の良い工事につながることになります。
- 5.諦めない
法律に関係するトラブルに巻き込まれると、諦めてしまいたくなるかもしれません。しかし、建物の工事は短い期間で終わりますが、住み続けるのは一生。ですから諦めずに解決に向けて努力することが大切です。そしてそのためには日頃から相談できる人を探しておくことも重要です。

【曳家の法律よくある質問 (FAQ)】

曳家にはどのような法律が関係しますか?
主に建築基準法、道路法、民法、消防法、都市計画法などが関係します。その他、文化財保護法や景観法、各自治体の条例なども関わってくる場合があります。
曳家の許可申請は誰が行うのですか?
原則的には、曳家を依頼する施主が行います。しかし、煩雑な手続きとなるため、建築士に代行してもらうケースが一般的です。代行を依頼する場合は、委任状を作成する必要があります。
関連記事
曳家での建築確認のコツ!建築基準法・既存不適格など曳家先生が解説!
曳家で近隣の建物に損害を与えた場合の責任は?
基本的に曳家工事を請け負った業者に責任があります。ただし、契約内容や損害の状況によっては、施主にも責任が及ぶ場合があります。業者の賠償保険加入状況を確認しましょう。
曳家を依頼する際に確認すべき業者の資格は?
建設業法に基づく建設業許可(建築工事業など)の有無を確認しましょう。また、業者の実績や賠償責任保険への加入状況、加えて、現場監督の国家資格の施工管理技士、作業員の専門資格の曳家技術士、作業に必要な運転士免許、技能講習、特別教育など取得しているかを確認しましょう。
関連記事
【曳家の業者選び】評判・口コミで選ぶ優良会社|選び方のコツも解説【チェックシート付き】
ーーー
大切な家を守るために、知っておきたい法律の知識
法律は、私たちの生活を守るためにあります。しかし同時に、法律は複雑で、一般の人には理解しにくいと感じられることもあるものです。特に曳家工事のような専門性の高い分野では、法律に関連するトラブルが発生するリスクも高くなり、法律に関係するトラブルに巻き込まれると、損をしてしまうケースも少なくありません。
しかし、今回ご紹介したコツを参考にすることで、法律トラブルを回避し、損をすることを防ぐことができます。五月女建設では法律の専門家ではありませんが、曳家に関する法律について幅広くご相談に乗ることができます。
- 専門業者ならではの知識と経験で、あなたの疑問や不安にお答えします。
- 第三者的な立場から、客観的なアドバイスを提供します。
- あなたの心に寄り添い、最後までサポートします。
まずはお気軽にご相談くださいね。
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
また曳家に関する法律の第三者的なアドバイスが欲しい方、不明な点等ある方などありましたら、日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女が相談に乗りますので、曳家先生へのウェブ相談、もしくは五月女建設のお問合せフォームでご連絡くださいね。あなたの身に寄り添った立場で協力させて頂きます。
出典
「住宅業界に関連する 民法改正の主要ポイント(国土交通省)」