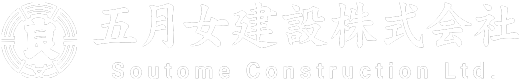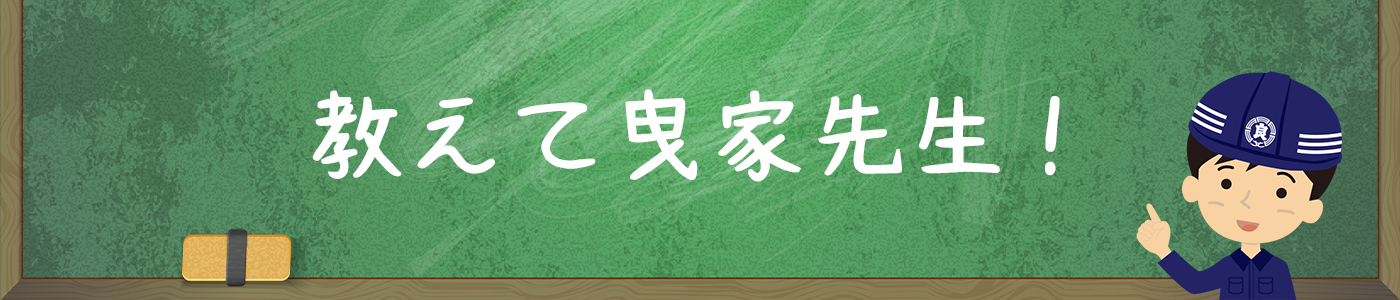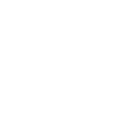【2025年4月版】曳家での建築確認のコツ!建築基準法・既存不適格など曳家先生が解説!
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! ~絶対に損しない建築確認のコツ~
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
こんにちは曳家先生です。前回は、「絶対に損しない工法のコツ」についてお話ししました。今回は、「絶対に損しない建築確認のコツ」についてお話しします。

大切な住まいを移動させる「曳家(ひきや)」工事。大規模な工事だからこそ、「建築確認」という聞きなれない手続きに頭を悩ませていませんか?「そもそも建築って何?」「なぜ曳家にも建築確認が必要なの?」といった疑問から、2025年4月にはさらに厳しくなる「4号特例の縮小」や、古くからの建物に影響する「既存不適格」といった専門用語まで、不安は尽きないかもしれません。
でもご安心ください。今回の「教えて曳家先生!」では、曳家の専門家である私たちが、あなたが絶対に損をしないための建築確認の「コツ」を徹底解説します。複雑に感じる建築基準法も、具体例を交えながらわかりやすくご説明し、あなたの疑問や不安を解消します。
このブログを読んで、曳家に関する建築確認の知識を深め、安心して曳家工事を進めるための一歩を踏み出しましょう。
そもそも建築って何?建築基準法での「建築」の定義
そんなこと言われたってシンプルに家を建てることが「建築」じゃないの? って誰しも思いますよね。
実は建築基準法では「建築」=「建物をつくる行為」として次の4種類の「行為」を「建築」として定義しているんです。
※「修繕」、「模様替え」については、今回は説明しません。
1.新築
「新築」とは建物のない更地に建築物をつくることを言います。また敷地をまたいだ曳家工事(曳き移転)も新築として定義されます。

※他の敷地の建築物を曳移転で更地に移動する場合も建築基準法の新築となります。
2.増築
「増築」とは敷地内の建築物の建築面積や床面積・延べ面積を増加させることを言います。一棟としての増築、別邸としての増築のどちらもこれに含まれます。
3.改築
「改築」とは建築物の一部か全部を取壊し、用途や構造、規模を変えずに建築物を作ることを言います。ただし用途・構造・規模の著しく異なる、全部建替は新築、一部建替は増築となります。
4.移転
「移転」とは同一敷地内での建物の移動を言います。同一敷地内での「移転」は既存不適格扱いとして、建築当初の建築基準法への適合が求められます。また、敷地をまたいだ曳き移転(新築)であっても、特定行政庁の認定を受けることで制限緩和により既存不適格扱いを受けることがあります。
つまり、
- 同一敷地内の移動:既存不適格扱い

- 他の敷地からの移動:認定により既存不適格扱い

となります。
また特定行政庁から次の5つの認定を受けることができれば既存建築物に制限緩和(技術的助言)があります。
- 上部構造の移転で前よりも悪くならないこと
- 移転の周囲に与える影響が少ないこと
- 外壁等の延焼のおそれのある部分の防火措置を行っていること
- 用途地域、容積率、建ぺい率などの集団規定は移転敷地に適合させること
- 周囲の環境への影響、許可などの実績を勘案すること
これらの建築行為を行うためには、一部の例外を除いて建築確認申請を通して建築基準法への適合を確認審査してもらうことが大切です。
曳家をする建物の中には、その曳家の対象となる建築物が手続きや避難、構造規定など、参照すべき建築基準法の規定に適合しないまま作られた違反建築物であることもあります。
その場合には移転の確認申請を取る前に建築士による調査・是正・報告書の作成が必要になったり、そもそも曳家工事ができない建築物が含まれることもあるので、曳家業者の担当者が建築基準法の最低限の知識を有するとともに、計画段階から知見ある建築士との共同計画が重要になってきます。
※この建築基準法上の「建築行為」における「曳き移転」、「移転」の概念は非常に重要になってくるので、理解しておくことが重要です。

なぜ曳家にも建築確認が必要なの?
なぜ曳家工事にも建築確認が必要なのか?
それは、建築基準法6条では「建築主は、特定の建築物を建築、増築、大規模修繕、大規模模様替えする場合、工事着手前に確認申請を行い、建築主事の確認を受ける必要がある」と定められているからです。
確認申請の主な目的は、「建築計画が建築基準法やその他の関連法規に適合しているかを第三者がチェックし、違反建築物の建設を防ぐこと」です。
つまり、建築主、これから住む人とその周囲に住む人の生命と財産を守るために建築基準法という法律の下で計画、チェックを行う仕組みなんですね。
曳家工事でも大切なのは工事をした後、ずっとその建物に住み続ける方の生命と財産を守る義務があるのです。
さて、確認申請が必要な建築物は以下の通りです。
1.特殊建築物(1号建築物)
面積100㎡以上の一般よりも強い制限を課す建築物を特殊建築物と言います。映画館・病院・学校などの公共性の高い建築物がこれに該当します。
2.木造建築物(2号建築物)
3階以上、面積500㎡以上、高さ13m以上、軒高9m以上のいずれかに該当する大規模な木造建築物の事を2号建築物と言います。木造かつ規模が大きいことで災害時の避難や防火上の措置に対し、厳しい制限があります。
3.木造以外の建築物(3号建築物)
2階以上、面積200㎡以上のいずれかに該当する木造以外の鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造などの建築物のことを3号建築物と言います。なお、鉄骨造であっても面積が200㎡未満の平屋建て車庫などは4号建築物に含まれます。
4.上記1、2、3、以外の建築物(4号建築物)
1号、2号、3号以外の建築物を4号建築物と言います。4号建築物には「4号特例」と呼ばれる緩和措置が適用されます。
具体的には
木造の場合:
- 2階建て以下
- 延べ面積500平方メートル以下
- 最高高さ13メートル以下
- 軒高9メートル以下
非木造の場合:
- 平屋建て
- 延べ面積200平方メートル以下
これらの条件を全て満たす建築物が4号建築物として分類されます

この特例により、建築確認申請の際に次の2つの簡略化が認められています
- 建築確認審査の一部項目が対象外となる
- 構造計算書の提出が不要
これらの特例により、4号建築物の建築確認手続きが簡素化されています。

ただし、2025年4月から「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(4号特例)の縮小が措置され、建築主・設計者の行う建築確認の申請手続きも変更されます。
つまり、「4号特例」が変更になるため、建築士への相談が必要です。
無料で今すぐ相談!※「建築基準法についての相談希望」と記載ください。
【2025年改定建築基準法とは!?】|その目的、内容、曳家への影響とは?
1. 改正の背景と目的
今回の建築基準法改正の背景には、地震対策や省エネルギーの推進、持続可能な社会の実現が挙げられます。特に、耐震性の向上は日本の地理的特性を考慮した重要な課題であり、これにより建築物の安全性が高まります。また、省エネ化の推進は、環境負荷の軽減とエネルギーコストの削減を目的としています。木造建築の促進も、地域の特性を活かした持続可能な建築を目指す動きの一環です。
移転工事に関連する改正点としては、既存不適格建築物の扱いや、移転先の土地における法的要件の厳格化が挙げられます。これにより、移転工事がより安全で効率的に行われることを目指しています。
2.移転工事に関連する改正点
1. 4号特例の縮小(新2号建築物が審査省略制度の対象、構造・省エネ関連の図書の提出)
【建築基準法第6条第1項】
「木造2階建て」、「木造平屋建て」のすべての建築物が4号建築物として、審査省略制度の対象だったことが、「木造2階建て」、「延べ床面積200㎡を超える木造平屋建て」は新2号建築物となり、審査省略制度の対象外に変更となります。
※なお、「延べ床面積200㎡以下の木造平屋建て」は新3号建築物となり、引き続き審査省略制度の対象となります。
また4号建築物は確認申請書・図書(一部図書の省略)であったことが、新2号建築物(「木造2階建て」、「延べ面積200㎡を超える木造平屋建て」)は「構造関係規定等の図書」+「省エネ関連の図書」の提出が必要になります。
・・・つまり、一般的な「木造2階建て」の住宅は確認申請が厳しくなると言えます。

2025年4月から4号特例が変わります。(国土交通省)
2.省エネ基準への適合義務化
延べ床面積300㎡以上の建築物に義務化されていた省エネ基準への適合が、改正後はすべての建築物に対して義務化されます。
一般的な「木造2階建て」の住宅が敷地をまたいだ曳家工事(曳き移転)を行う場合も新築として定義されるので、この省エネ基準の適合義務範囲内になります。
・・・ただし「移転」における「同一敷地内移転」や、認定を受けた「他の敷地からの移転」は既存不適格扱いになります。
※詳しく担当自治体の建築指導課より指導を仰いで下さい。

3.構造規制の合理化
【建築基準法第6条の3第1項】
小規模伝統木造建築物にかかる構造計算適合性判断の特例
〇 通常は構造計算によることなく仕様規定に適合させることにより構造安全性が確保される小規模の建築物であっても、伝統的構法等で一部の仕様規定を満たせない場合、高度な構造計算により構造安全性を確認している。(第20条第1項第4号ロ)
〇 小規模建築物であっても、高度な構造計算により構造安全性を検証した場合、建築確認における構造計算の審査に加え、構造計算適合性判定による複層的な確認が必要。(法第6条の3第1項)
↓↓改正↓↓
〇 小規模な伝統的木造建築物等(法第20条第1項第四号に掲げる建築物)について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定を不要とする。
・・・つまり、一部条件を満たせば小規模伝統的木造建築物においては構造計算が不要になります。
既存不適格|・・・建築基準法の抜け道!?
【建築基準法第3条第2項】

さて次は、曳家工事でよくある「既存不適格」について解説していきます。
建築基準法における既存不適格とは、建築当時は適法であった建築物が、その後の法改正によって現行の建築基準法に適合しなくなった状態を指します。この概念は、法律の遡及適用を避け、既存の建物所有者の権利を保護するために設けられました。
既存不適格の具体例としては以下のようなものがあります
- 建ぺい率や容積率の変更により、現在の基準を超えている建物
- 耐震基準の強化により、現行の耐震性能を満たしていない建物
- 防火地域の指定変更により、現在の防火基準を満たしていない建物
法的な観点から見ると、既存不適格建築物は以下のような扱いを受けます:
- 現状のまま使用し続けることが可能(そのまま継続して利用する場合には、遡及適用はされません)
- 増築や大規模な改修を行う場合は、現行の基準に適合させる必要がある。(ただし、計画の内容によって様々な緩和措置が設けられています)
- 建て替えの際は、新しい建築基準法に完全に適合させる必要がある。
近年の法改正や動向として、以下の点が挙げられます:
- 2018年の建築基準法改正により、既存不適格建築物の増築に関する規制が一部緩和された
- 耐震改修促進法の改正により、耐震性能が不足する既存不適格建築物の所有者に対して、耐震診断や改修の努力義務が課されるようになった
- 地域の特性に応じた柔軟な対応を可能にするため、一部の基準について地方自治体が条例で独自の規制を設けることが可能になった
法的根拠
既存不適格に関する主な法的根拠は以下の通りです:
- 建築基準法第3条第2項:既存不適格建築物に対する基本的な取り扱いの規定
- 建築基準法第86条の7:既存建築物に対する制限の緩和の規定
- 建築基準法施行令第137条〜第137条の15:具体的な緩和措置の内容の規定
既存不適格と違法建築物の違い
既存不適格と違法建築物は異なる概念です:
- 適法性:
・既存不適格:建設時には適法
・違法建築物建設当時から法的に問題があったもの - 建築確認の有無:
・既存不適格:当時の法律に基づいて許可を取得している(もしく建築当時に建築基準法が施行されていない)
・違法建築物:当時の法律に基づいて建築許可を取得していないか、許可内容と異なる形で建てられている。
つまり、その建築物が建てられた年月日とその当時の建築基準法が既存不適格と違法建築物を分ける判断基準となります。
余談ではありますが、建築基準法の施行されたのは昭和25年ですので、それ以前の建築物に関しては、既存不適格扱いとなります。(昭和25年以降の建築行為(増築、改築など)があった建築物を除く)
既存不適格は、都市の安全性向上と既存建築物の有効活用のバランスを取る上で重要な概念です。曳家工事において建物の所有者は、自身の建物が既存不適格に該当するかどうかを確認し、必要に応じて専門の建築士に相談することをおすすめします。
曳家に関わる建築行為の「新築における敷地をまたいだ曳家工事(曳き移転)」、「移転」の概念とともに「既存不適格」を理解することでスムーズな曳家工事の確認申請が可能になります。
建築工事には、工事着工前から工事中、工事完了後と様々なリスクが伴います。これらのリスクからお客様生命と財産を守るための法律が建築基準法です。建築基準法を理解し、建築確認を理解することで、生命と財産を守ることができます。
ここまで、曳家工事を含む建築の定義や建築物の種類についてお話ししました。ただでさえ分かりにくい建築基準法ですが、2025年4月には4号特例(審査省略制度)の対象範囲が変更になります。建築確認について分からないことがあれば、どんなに小さいことでも身近な業者さん、建築士さんに相談してくださいね。
無料で今すぐ相談!※「建築基準法についての相談希望」と記載ください。
また教えて曳家先生では建築確認以外の曳家にまつわる法律についても「教えて曳家先生! 第五話 ~絶対に損しない法律のコツ~」で触れているので、興味のある方、よくあるトラブルを回避したい方は参考までに見てみてください。

曳家工事と建築確認に関するQ&A
Q1: 建築基準法における「建築」とは具体的に何を指しますか?
A1: 建築基準法では、「建築」は建物を新たに建てる新築だけでなく、敷地をまたぐ曳家工事も新築と定義されます。その他に、面積を増やす増築、一部または全部を取り壊し、用途や規模を変えずに建物を建てる改築、そして同一敷地内で建物を移動させる移転の計4つの行為を指します。
Q2: 曳家工事でも建築確認が必要ですか?
A2: 曳家工事においても、建築基準法第6条に基づき建築確認が必要です。これは、建築計画が法規に適合しているかを第三者がチェックし、違反建築物の建設を防ぐことで、住む人や周囲の人の生命と財産を守るためです。
Q3: 2025年4月の建築基準法改正で、曳家工事にどのような影響がありますか?
A3: 主な影響は3点です。①「4号特例」が縮小され、一般的な木造2階建て住宅の確認申請が厳しくなります。また、②省エネ基準への適合が全ての建築物に義務化され、敷地をまたぐ曳家工事で新築扱いになる場合も対象です。一方で、一部の小規模伝統的木造建築物では③構造計算適合性判定が不要になる場合があります。
Q4: 改正によって、一般的な「木造2階建て」の住宅への影響はありますか?
A4: はい、一般的な「木造2階建て」の住宅は、改正により「新2号建築物」となり、確認申請が厳しくなります。構造や省エネに関する図書の提出が必要になります。ただし、同一敷地内の移転は既存不適格扱いとなり、敷地をまたぐ移転においても移転認定(令137条の16第2号)を受けることで既存不適格のまま移転が可能となります。
Q5: 「既存不適格」とは何ですか?
A5: 「既存不適格」とは、建築当時は適法だった建物が、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった状態を指します。これは、法律の遡及適用を避け、既存の建物所有者の権利を保護するために設けられた概念です。
Q6: 「既存不適格」と「違法建築物」の違いは何ですか?
A6: 既存不適格は建築当時は適法でしたが、違法建築物は建設当時から法的に問題があったものです。つまり、建築された時点での法律への適合性の有無が両者を区別する基準となります。
Q6: 曳家工事を検討する際、業者選びで特に重要なことは何ですか?
A6: 曳家工事は専門性が高いため、建築基準法に関する知識が豊富で、かつ経験と実績のある業者を選ぶことが重要です。また、お客様の不安を解消するために丁寧なカウンセリングと分かりやすい説明をしてくれるか、そして適正な見積もりと無料相談に応じてくれるかも確認しましょう。
Q7: 曳家工事において、「移転」と「新築(曳き移転)」の概念はどのように扱われますか?
A7: 同一敷地内での移動は「移転」として既存不適格扱いとなります。一方、他の敷地からの移動は「新築」として定義されますが、特定行政庁の認定を受けることで制限緩和により既存不適格扱いを受けられる場合があります。
Q8: 曳家工事を行う建物が「違反建築物」だった場合、どうなりますか?
A8: 曳家の対象となる建物が違反建築物である場合、移転の確認申請を取る前に建築士による調査・是正・報告書の作成が必要になります。場合によっては、そもそも曳家工事ができない建築物である可能性もあります。
Q9: 2025年4月からの4号特例縮小により、確認申請の際に追加で必要となる書類はありますか?
A9: はい、「新2号建築物」(木造2階建て、延べ面積200㎡を超える木造平屋建て)に該当する場合、従来の確認申請書に加え、「構造関係規定等の図書」と「省エネ関連の図書」の提出が必要になります。ただし、同一敷地内の移転、移転認定を受けた移転はこの限りではありません。
Q10: 建築基準法はなぜ一般の人には理解しにくいと感じられることが多いのですか?
A10: 建築基準法は複雑で難解な内容が多く、専門用語も多用されるため、一般の方には理解しにくいと感じられることが多いです。特に曳家工事のような専門分野では、工事に関わる建築士や曳家業者でも関連法規を全て把握しているとは限らない現状もあります。
Q10: 曳家工事の専門業者に相談したい場合、どこに連絡すれば良いですか?
A10: 曳家工事を検討しており、信頼できる業者が見つからない場合は、ブログ記事で紹介されている日本曳家協会認定の曳家指導士である五月女建設のお問い合わせフォームから相談できます。
ーーー
生命と財産を守る建築基準法だけど・・・
建築基準法は私たちの生活、つまり生命と財産を守るために存在します。しかし、複雑で難解な内容も多く、一般の方には理解しにくいと感じられることも少なくありません。また特に曳家工事のような専門性の高い分野では実は工事に関わる建築士や曳家業者でも関連する法律を把握しているとは限らないのが現状です。
だからこそ実績と経験に基づいてお客様の状況に合わせた適切なアドバイスを提供できる業者が大切です
そして私たちは・・・
お客様の不安や疑問を解消するために
丁寧なカウンセリング:お客様のご要望を丁寧に伺い、不安や疑問を解消します。
分かりやすい説明:専門用語をできるだけ使わずに、お客様に分かりやすい説明を心掛けます。
見積もりの詳細:費用内訳を詳細に説明します。
お客様の安心のために
無料相談:費用や工期など、建築確認申請の際にわからないことなど何でもお気軽にご相談ください。
現地調査:建物の状態や周辺環境を調査し、無理のない工事の提案とその説明を心掛けます。
アフターフォロー:工事完了後も定期的に連絡を取り、建物の状態を確認します。
などをお客様の安心安全な曳家工事のために、全力でサポートをして参ります。
ーーー
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
もし身近に信頼できる曳家さんがいない場合は日本曳家協会認定の曳家指導士、五月女がお答えします。ぜひ五月女建設のお問合せフォームにお悩みを曳家先生へのウェブ相談、もしくは五月女建設のお問合せフォームでご連絡くださいね。あなたの身に寄り添った立場で法律面、施工面、費用面など持てる知識と経験の限り、誠心誠意お答えさせて頂き、あなたの「絶対損しない建築確認」に協力させて頂きます。

参考文献
・世界でいちばんやさしい建築基準法(著:谷村広一)
・小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例(国土交通省)
・建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(国土交通省)