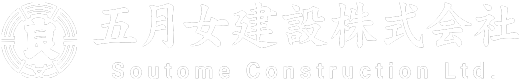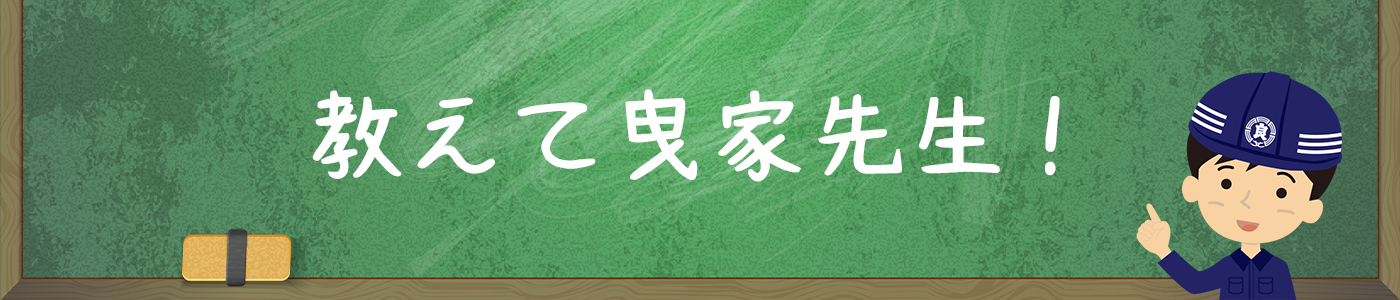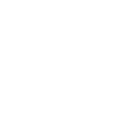【液状化現象】地震による被害を防ぐ!対策と沈下修正工事|原因・対策・再沈下防止
公開日: 最終更新日:
教えて曳家先生! 第十六話 ~絶対に損しない液状化現象のコツ~
「「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
こんにちは曳家先生です。前回は、「絶対に損しない床下浸水のコツ」についてお話ししました。今回は、ニュースでよく見る地震での建物の損壊、「液状化現象」について、その仕組みや特徴についてお話します。
~備えあれば憂いなし!「液状化現象」を徹底解説!~
液状化現象とは?そのメカニズムを解説!
地震の恐ろしい落とし穴:液状化現象とは
ニュースを見ていると、地震による建物の倒壊や火災の映像に目が行きますよね。でも実は、地震の恐ろしさはそれだけじゃないんです。地面そのものが液体のように変化する「液状化現象」が、私たちの生活を脅かす大きなリスクとなっているんです。
液状化現象とは、地震の際に地下水位の高い砂地盤が振動によって液体状になる現象です。まるで地面が泥水のようにドロドロになってしまう、そんなイメージでしょうか。
この現象は、特に水を多く含んだ砂の地盤や埋立地で発生しやすく、そんな地盤に地震による強い揺れが加わることで、地盤が一時的に支持力を失い、建物や構造物が沈下したり傾いたりすることがあります。
なぜ起こるの!?:液状化のメカニズム
液状化が起こりやすいのは、主に地下水位の高い、ゆるい砂地盤です。地震の激しい揺れによって、砂粒子の間の結合が切れ、水と砂が分離し、砂が水に浮いた状態になります。
つまり、砂の粒子がバラバラになり、その隙間に水が流れ込むことで、地面全体が液体のようになってしまうんです。
そのステップを4つの段階で説明します。
- 通常時:砂粒同士が接触し、摩擦により地盤の安定を保っている。

- 地震時:地震の揺れにより地盤が変形し、砂粒間の隙間にある水の圧力が上昇。
- 液状化:水圧の上昇により砂粒同士の接触が弱まり、地盤全体が泥水状になる。

- 地震後:砂粒が沈降し、地盤が沈下。過剰な水圧により噴砂や噴水が発生

恐ろしい液状化現象はいくつかの条件が重なることによって、発生します。
次は具体的にどんな被害の例があるのかを見ていきましょう。
どんなことが起こるの?実際の被害を解説
他人事じゃない!:日本であった被害例
- 新潟地震(1964年): 液状化によって県営アパートが大きく傾く被害が発生しました。
- 阪神淡路大震災(1995年): 神戸港の港湾施設が液状化を主因とする大きな被害を受けました。
- 東日本大震災(2011年): 関東地方で96市町村で液状化被害が確認され、特に東京湾周辺では広範囲にわたる液状化現象が発生しました。
特に東日本大震災の液状化被害は記憶に新しいのではないかと思います。では、液状化がおこると私達の生活にはどんな影響が起こるのでしょうか?
液状化が引き起こす被害とは?:私たちの暮らしに迫る危機
液状化現象は、まるで地面が牙をむくように、私たちの生活基盤を容赦なく破壊します。その被害は、想像を絶するほど甚大です。
- 地盤沈下、道路陥没や亀裂: 道路や地面に深い亀裂が走り、建物は傾き、基礎部分がむき出しになることも。住み慣れた家や近隣地域が道路の陥没や埋設水道管や下水などのライフラインの切断により、一瞬にして生活できない空間に変わってしまうのです。
- 噴砂:地中の砂が、水と混ざって地表に噴き出します。

- 軽い地中構造物の浮上: 地下深く埋まっているはずのマンホールや下水管が、まるで地底からの使者のように地上に浮き上がります。道路は陥没し、水道やガスなどのライフラインが寸断され、復旧には長い時間を要することもあります。

- 重い構造物の傾斜・倒壊:液状化現象による急激な地耐力の低下により、重い建物が傾いたり、沈下してしまうことがあります。 一度傾いた建物は、もはや安全な住まいとは言えないかもしれません。最悪の場合、傾いた建物が倒壊する可能性もあります。
もし建物に「ひび割れ」が起きてしまった時は「教えて 曳家 先生! 第十一話 ~絶対に損しない ひび割れ 防止のコツ~」」を参考にしてください。
液状化現象の被害は、私たちの生活を破壊してしまう力を持っているんですね。次は液状化しやすい地形、条件などに触れていきます。
液状化が発生しやすい地形と条件とは?
私の家は大丈夫?:液状化が発生しやすい地形と条件とは?
現在では、過去の事例から液状化現象が起きやすい地形や条件がわかってきていると言われています。それでは一体どんな地形・条件で液状化現象が発生しやすいのでしょうか。
液状化が起こりやすい地形
- 埋立地・干拓地: 人工的に作られた埋立地や干拓地、特に埋め立て年代の浅い埋立地や砂鉄・砂礫を採掘した跡地、沢・谷埋め盛土の造成地は、液状化が発生しやすい地盤です。他に注意が必要な具体的な土地としては砂州・砂礫州、旧河道、旧池沼などです。
- 河川沿い・海岸沿い: 河川沿い、海岸沿いは、地下水位が高く、砂地盤が広がっているため、液状化のリスクがあります。三角州、海岸低地、後背湿地、干拓地などがこれにあたります。
- 過去の液状化履歴がある場所: 過去に液状化が発生した場所は、再び液状化する可能性があります。
液状化が起こりやすい条件
- 砂質土(砂の地盤):粘性土では液状化現象は発生せず砂質土において発生します。
- 地下水位: 液状化現象は土中の水分による摩擦力を失わせる現象なので、地下水位が低いところでは発生しません。地下水位が地表面から10m以内である場合、要チェックです。
- 緩い砂地盤: 海岸や河口付近、埋立地などの砂地だった場所で多く見られます。
- 大きな地震の揺れ: 震度5以上の揺れで急激に液状化現象が増えるようです。また地震の規模・継続時間などによって被害の程度が異なります。
もしかして!?と思ったら・・・
- 国や自治体が公表しているハザードマップで確認できます。 ハザードマップには、液状化の危険性の高さが示されています。
- 国土交通省が提供する「ハザードマップポータルサイト」で、全国の液状化ハザードマップやボーリングデータなどを閲覧できます。
- 過去に発生した液状化被害の履歴を地図上に示した「被災履歴図」や、液状化の可能性の判断に有効な埋立地等を示す「地形区分図」を参考にできます。 これらの資料は、国土交通省が公表しています。
- 自治体によっては、より詳細な液状化危険度マップを公表している場合があります。
- 地盤調査会社に依頼して、地盤調査を行うこともできます。
どこから手を付けていいかわからない方は、スマホでも簡単に液状化現象を調べることができるツール、「重ねるハザードマップ」を利用してみましょう。あなたの家の液状化リスクが一目瞭然でわかりますよ。
ただし、液状化危険度マップは、過去の地震被害データや地盤調査結果に基づいて作成されていますが、あくまでも目安であり、必ずしも正確に液状化の発生を予測できるわけではありません。現に 東日本大震災では、液状化危険度マップで危険性が低いとされた地域でも、液状化被害が発生しました。ですので、液状化危険度マップで危険性が低いとされていても、絶対に安全というわけではありません。 地盤の状況は場所によって異なり、マップでは表現しきれない細かな違いがあるためです。
特に、重要な施設や、液状化による被害を受けたくない場合は、専門家に相談の上、液状化対策を検討することをお勧めします。
液状化現象による沈下・傾斜の確認ポイント
ご自宅の沈下や傾斜が液状化現象によるものかどうか、以下のポイントを確認してみましょう。
- 建物全体の傾き: 水平器などで確認できます。目視で明らかに傾いている場合もあります。
- 基礎のひび割れ:基礎部分に亀裂が入っている場合、不同沈下の可能性があります。
- 外壁や内壁のひび割れ: 特に窓やドアの角から斜めにひびが入っている場合は要注意です。
- ドアや窓の開閉不良: 建物が歪むことで、ドアや窓がスムーズに開閉できなくなることがあります。
- 外構の沈下やひび割れ: 塀や地面が沈下したり、ひび割れたりしている場合も、液状化の影響が考えられます。
- 庭や道路への噴砂: 地震後、庭や道路に砂が噴き出している場合、液状化が発生した可能性が高いです。 これらの症状が見られる場合は、液状化現象による沈下・傾斜の可能性を考慮し、専門家への相談を検討しましょう。
液状化対策工事の種類
知って得する:液状化対策工事の種類
液状化対策には、大きく分けて以下の2つの方法があります。
- 「住宅が建ったままの状態」でできる対策(沈下修正工事)
- 表層地盤改良工法:ウレタン系などで浅い部分から建物を上げる方法
- 鋼管杭工法:建物重量を反力として支持地盤まで鋼管杭を打ち込み、建物の沈下を修正する工法
- 薬液注入工法:水ガラス系、ウレタン系、モルタル系などの薬液を地盤に注入して強度を増加、沈下を修正する工法
- その他:その他、建物の土台から上を上げる土台上げ工法、基礎下に鉄製やコンクリート製の耐圧盤を設け、その反力で建物を持ち上げる耐圧盤工法もあります。
- 「建て替え・新築時」にできる対策
-
- 表層地盤改良工法:セメント系固化材を使用して地表から最大2メートルまでの浅い部分の地盤を改良する方法
- 深層混合処理工法:セメント系固化材と水を混ぜたスラリーを使用して、現地の土と混合しながら柱状の改良体を形成する工法、最大50m程度の深さまで施工可能
- 鋼管杭工法:鋼製の杭を地中に打ち込んで建物を支える工法
- ベタ基礎工法:建物の底面全体を鉄筋コンクリートで覆う基礎工法
液状化対策工事の比較表
| 工法 | 特徴 | 適用深度 | 工期 | コスト | 主な適用 |
| 表層地盤改良 | 施工が簡便で工期が短い (1~2日程度) 多様な土質に対応可能 経済性が高い | ~2m | 1~2日 | 低 30~50万円程度 | 小規模建物や 中層建物の基礎 道路や駐車場の 沈下防止 擁壁や看板の基礎 |
| 鋼管杭 | 高い耐久性 (50年以上の耐用年数) 高い支持力 環境への影響が少ない | ~30m | 7~20日(既設建物) 1~3日(建替・新築) | 高(既設建物) 中(建替・新築) | 中~大規模建物 |
| 薬液注入 | 地盤強化 止水性の向上 施工の柔軟性 地下水汚染のリスク | 可変 | 可変 | 中 | 多様など質条件に 対応可能 液状化対策、止水 |
| 深層混合処理 | 高い耐久性 (50年以上の耐用年数) 狭小地でも施工可能 環境への影響少ない | ~50m | 2~4日 | 中 | 中規模建物、 不同沈下対策 |
| ベタ基礎 | 耐震性の向上 湿気とシロアリ対策 不同沈下の低減 材料費・施工費が高くなる。 | 表層 | 可変 | 中~高 | 住宅、軟弱地盤 |
液状化対策は、建物の構造や地盤の状況に合わせて、適切な工法を選択することが重要です。 近くの建築士や、地盤調査会、沈下修正の専門業者に相談し、最適な工法を選定してもらいましょう。
すでに建っている建物の沈下修正工事については「教えて曳家先生! 第十四回 ~絶対に損しない地盤沈下~」を参考にしてくださいね。
さて、工事を行うにしても、液状化対策に関する法律もチェックしなくてはいけません。
次は液状化対策に関する法制度の解説をしていきますね。
液状化対策に関する法制度
液状化対策に関連する主な法律には、以下のようなものがあります。
- 宅地造成等規制法: 盛土を行う場合に、地盤の沈下や崩壊を防ぐための対策を義務付けています。
- 都市計画法: 宅地造成等規制法と同様に、盛土を行う際の対策を定めています。
- 公有水面埋立法: 都道府県知事が埋め立てを許可する条件として、災害防止に十分配慮することを求めています。 しかし、具体的な液状化対策基準は示されていません。
- 建築基準法: 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重や外力を安全に地盤に伝え、地盤の沈下や変形に対して安全なものとするよう規定しています。 しかし、木造2階建てなどの小規模建築物では、液状化の可能性の判断は設計者に委ねられており、具体的な規定はありません。
- 宅地建物取引業法: 重要事項説明において、過去に液状化被害があった土地や、沈下の可能性がある土地については、説明義務があります。 しかし、液状化危険度そのものは重要事項説明の対象ではありません。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法): 液状化対策についての義務は課していませんが、震災や液状化をきっかけに住宅に欠陥があったことが原因で被害が発生した場合は、瑕疵担保責任の対象となります。

液状化に関連する法律は複雑に感じることも多いと思いますが、万が一が起きてしまった時のために「知る」事が重要です。
「法律はなんとなくわかったけど、実際のお金は?」、「保険は適用されるの?」という疑問もあるかと思います。
それでは液状化の被害に遭った場合、保険の適用はあるんでしょうか?
液状化被害に遭った場合、地震保険は適用されますか?
地震保険は液状化被害にも適用されます。 地震を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害が補償対象となるためです。液状化被害の評価は、建物の損傷の程度に加えて、地盤の沈下や傾斜の程度に応じて行われます。 例えば東日本大震災後には、液状化特有の建物の傾斜や沈下といった損害に着目した損害認定方法が基準に追加されました。
液状化被害に関する保険や支援制度
地震保険で、液状化被害に対する保険金を受け取るには?
地震が発生したら、加入している地震保険の保険会社に連絡し、被害状況などを報告しましょう。
- 保険会社からの連絡を待たずに、ご自身で写真や動画などで被害状況を記録しておきましょう。
- 保険会社が、損害調査を行い、損害の程度を判定します。
- 損害の程度に応じて、保険金が支払われます。
保険があるとないとでは大違い。今加入されている保険の地震保険の項目を確認しておくとよいでしょう。
次は保険以外の公の支援制度についてです。
液状化被害に遭った時の支援制度
被害の程度や、お住まいの地域によって異なりますが、以下のような支援制度があります。
- 被災者生活再建支援制度: 住宅が全壊・半壊などの被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給する制度。
- 災害復興住宅融資: 住宅の建設や購入資金を、低金利で融資する制度。
- 災害復興宅地融資: 宅地の購入資金を、低金利で融資する制度。
その他、罹災証明書を提出することによって災害支援金などを受け取ることもできるので、各自治体に問い合わせておくとよいでしょう。
それでも、「地震が不安」、「液状化現象の対策をすることはできないの?」という方もいるかと思います。
そんな方へ液状化対策のベストなタイミングを解説します。
いつ行う?液状化対策
結局、液状化対策は、いつ行うのが良いですか?
新築時に行うのが、最も効果的かつ経済的です。 つまり、新築時に液状化対策を行うことで、建物の設計の自由度が高くなり、より適切な対策を実施できます。 また、住宅が存在しない状態で施工できるため、費用も抑えられます。
ただし、既存の住宅の場合でも、大規模なリフォームや、ライフラインの更新工事を行う際に併せて検討すると良いでしょう。
液状化対策は、費用対効果や、将来のライフプランなども考慮して判断する必要があります。 専門業者や、自治体の相談窓口などに相談し、情報を収集した上で、判断することをお勧めします。
また液状化対策は、建物の安全性を高めるための有効な手段ですが、地震による被害を完全に防ぐことはできません。 日頃から、家具の転倒防止対策や、非常持出品の準備など、地震への備えをしておくことが大切です。
液状化現象による建物の沈下修正方法|主な工法と費用・期間
液状化現象によって沈下してしまった建物を修正するには、いくつかの工法があります。ここでは、主な工法とその費用・期間の目安について解説します。
アンダーピニング工法
アンダーピニング工法は、建物の基礎の下に新たな基礎を設けて建物を支え直す工法です。液状化によって地盤が緩んでしまった場合でも、より強固な地盤まで基礎を構築することで、建物の安定性を回復させることができます。費用は比較的高額になる傾向がありますが、確実性の高い工法と言えます。
費用相場:200万円~800万円程度
期間: 2週間~2ヶ月程度
ーーー
ジャッキアップ工法
ジャッキアップ工法は、建物をジャッキで持ち上げ、沈下した部分を水平に戻す工法です。比較的短期間で施工できる場合があり、費用もアンダーピニング工法より抑えられる傾向があります。ただし、建物の構造や状態によっては適用できない場合があります。
費用相場:150万円~600万円程度
期間:1週間~1ヶ月程度
ーーー
耐圧版工法
耐圧版工法は、建物の基礎の下に鉄筋コンクリート製の耐圧版を設け、面で建物を支えることで不同沈下を修正する工法です。アンダーピニング工法よりも費用を抑えられる場合がありますが、地盤の状態によっては適用できない場合があります。
費用相場:100万円~500万円程度
期間: 1週間~1ヶ月程度
ーーー
薬液注入工法
薬液注入工法は、地盤中に特殊な薬液を注入し、地盤を固めることで建物の沈下を食い止める工法です。比較的小規模な沈下や、他の工法と併用して用いられることがあります。費用は比較的抑えられますが、地盤の種類や状態によっては効果が得られない場合もあります。
費用相場: 50万円~300万円程度
期間: 数日~1週間程度
ーーー
どの工法が最適かは、建物の状況や地盤の状態によって異なります。専門業者と相談し、最適な工法を選びましょう。
液状化現象による沈下修正にかかる費用相場と内訳
液状化現象による沈下修正にかかる費用は、建物の状態や選択する工法によって大きく異なります。ここでは、費用相場と費用の内訳について解説します。
費用を左右する要因
液状化現象による沈下修正の費用は、以下の要因によって変動します。
選択する工法:アンダーピニング工法は比較的高額になり、薬液注入工法は比較的費用を抑えやすい傾向があります。
建物の規模と構造: 建物の面積や階数、構造によって、必要な材料や手間が異なり、費用に影響します。
沈下量と傾斜の程度:沈下や傾斜が大きいほど、大掛かりな工事が必要となり、費用も高くなる傾向があります。
地盤の状況: 地盤の強度や状態によって、適切な工法や必要な材料が異なり、費用が変わります。
付帯工事の有無:工法によっては外構の修繕やライフラインの復旧など、付帯工事が必要となる場合があります。
後悔しない!液状化による沈下修正業者の選び方
液状化現象による沈下修正は専門的な知識と技術が必要なため、業者選びは非常に重要です。信頼できる業者を選ぶことが、工事の成功と安心に繋がります。
液状化による沈下修正の実績と専門性
業者を選ぶ際に最も重要なのは、液状化現象による沈下修正の実績です。過去の施工事例を確認し、同様の被害状況の建物の修正経験が豊富かどうかを見極めましょう。また、国家資格の施工管理技士を始めとした建築や地盤に関する専門的な資格を持つ技術者が在籍しているかどうか、建物・地盤に対する知識が豊富かどうかも確認しましょう。
見積もりの内訳と保証内容の確認
複数の業者から見積もりを取り、費用の内訳が明確に記載されているかを確認しましょう。不明な項目があれば、必ず質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。また、工事後の保証内容についても詳しく確認し、万が一の事態に備えましょう。
アフターフォロー体制と口コミ・評判の確認
工事後のアフターフォロー体制が整っているかどうかも重要なポイントです。定期的な点検や、不具合が発生した場合の対応について確認しておきましょう。また、インターネット上の口コミや評判も参考に、実際に利用した人の声を聞いてみましょう。
複数の業者から見積もりを取り比較検討する
必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。見積もり金額だけでなく、担当者の対応や会社の信頼性なども考慮し、総合的に判断することが大切です。
費用を抑えるためのヒント
液状化現象による沈下修正の費用は高額になることもありますが、以下の点を意識することで費用を抑えられる可能性があります。
複数の業者から相見積もりを取る:
複数の業者から見積もりを取ることで、価格競争が生まれ、費用を抑えられる可能性があります。
火災保険の適用範囲を確認する:
加入している火災保険の内容によっては、液状化による損害が補償される場合があります。保険会社に確認してみましょう。
補助金制度を活用する:
自治体によっては、液状化対策に対する補助金制度がある場合があります。確認してみましょう。
費用だけでなく、工事内容や業者の信頼性も考慮して、総合的に判断しましょう。
液状化現象による沈下修正後の注意点と再発防止策
液状化現象による沈下修正工事が完了した後も、注意すべき点や再発防止のための対策があります。
定期的な点検とメンテナンス
沈下修正後も、定期的に建物の傾きやひび割れの状況を点検しましょう。早期に異常を発見することで、被害の拡大を防ぐことができます。また、専門業者による定期的なメンテナンスも検討しましょう。
正しい工法の選定
沈下修正工事の工法ごとにメリット・デメリットが存在します。例えば土台上げ工法は費用が安価で外構(庭や塀)を撤去することもありませんが、支持地盤から反力を得るという本質的な対策工法ではないため、地盤の種類によっては再沈下が起こることもあります。こういった工法ごとのメリット・デメリットを理解して、工法を選択することが重要です。
液状化対策としての地盤改良
過去に液状化現象が発生した地域では、将来的な再発に備え、地盤改良工事を行うことを検討しましょう。地盤改良工事には、表層改良、柱状改良、深層混合処理など、様々な工法があります。専門業者に相談し、適切な工法を選びましょう。
ハザードマップの確認と備え
お住まいの地域の液状化ハザードマップを確認し、液状化のリスクを把握しておきましょう。ハザードマップを確認することで、適切な防災対策を講じることができます。また、非常用持ち出し袋を用意するなど、日頃からの備えも大切です。
【液状化現象よくあるご質問 (FAQ)】

液状化現象による沈下修正の費用はいくらくらいかかりますか?
液状化現象による沈下修正の費用は、建物の状態や選択する工法によって大きく異なりますが、一般的には50万円から数百万円程度かかることが多いです。正確な費用は、複数の業者に見積もりを依頼して確認しましょう。
液状化現象による沈下修正の期間はどれくらいですか?
液状化現象による沈下修正の期間は、選択する工法や建物の規模によって異なりますが、数日から数ヶ月程度かかる場合があります。
液状化現象による沈下は火災保険で対応できますか?
加入している火災保険の内容によっては、液状化による損害が補償される場合があります。保険会社に確認してみましょう。
液状化現象による沈下修正業者を選ぶ際の注意点は?
液状化による沈下修正の実績、見積もりの内訳と保証内容、アフターフォロー体制、口コミ・評判などを総合的に判断し、信頼できる業者を選びましょう。必ず複数の業者から見積もりを取り、その見積内容や担当者の対応を比較検討することが大切です。
まとめ
液状化現象は、地震の被害を大きくする可能性があります。でも、事前に正しい知識を身につけて、しっかりと対策をしておけば、被害を最小限に抑えることができます。
また「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、日頃から防災意識を高め、いざという時に備えておくことが大切です。
この記事を読んで、液状化現象について少しでも理解を深めていただけたら嬉しいです。あなたの安全を守るために、ぜひ参考にしてください。
私たちは、長年にわたり培ってきた曳家工事・沈下修正工事のノウハウと、熟練した技術者の 専門知識を駆使し、お客様の家屋を安全かつ確実に液状化対策することをお約束いたします。材料の選定から設置、運用まで、すべての工程において、細心の注意を払い、お客様の大切な財産である家屋を確実に守ります。また家屋を守るだけでなく、その歴史や思い出も一緒に守ることが私たちの本来の仕事です。私たちは、「縁の下の力持ち」である仕事を通じて、お客様の大切な家屋と、そこに詰まった思い出を、未来へと繋ぐお手伝いをさせていただきます。
ーーー
「教えて曳家先生!~絶対に損しない○○のコツ~」では、曳家の専門業者だからこそ知っている絶対に損をさせないお得な情報、大切な情報について触れていきます。
曳家を検討されている方はぜひ読んで、絶対に損しない曳家と工事の後にも続く大切な生活に必要な情報を一緒に学んでいきましょう。
もし身近に信頼できる専門業者さんがいない場合は曳家先生への「ウェブ相談」、もしくは五月女建設の「お問合せフォーム」でご連絡くださいね。あなたの身に寄り添った立場で法律面、施工面、費用面など持てる知識と経験の限り、誠心誠意お答えさせて頂き、あなたの「絶対損しない液状化対策工事」に協力させて頂きます。
出典
「アンダーピニング工法 設計・施工マニュアル(新アンダーピニング工法等研究会)」
「曵家岡本口伝 建築士が沈下修正工事を相談されたら読む本(岡本直也)」
「地震被災建物 修復の道しるべ(一般社団法人日本曳家協会)」
「曳家業務 曳家のガイドブック基礎知識(一般社団法人日本曳家協会)」
「建物の傾きによる健康障害(日本建築学会)」